離乳食の進め方
離乳食
赤ちゃんは5から6か月頃まで母乳や育児用ミルクを飲んで成長します。そして、赤ちゃんはこの頃から1年くらいかけてゆっくりと「食べ物をかみつぶして飲み込む」ことを練習していきます。これが「離乳食」です
食べる楽しさや経験を増やしながら、
「食べる力」「食べる意欲」「生活のリズム」
を身につけさせてあげてください。家族と一緒に食事をすることで、赤ちゃんの情緒も育まれていきます。その過程を楽しみながら見守っていきましょう
授乳から離乳へ
1.離乳を始める前の栄養

赤ちゃんは成長に必要な栄養を母乳や育児用ミルクからとります。しっかり抱いて、優しく声をかけながら欲しがるだけあげましょう
2.離乳食の開始
生後5から6か月頃になったら離乳食を開始しますが、この時期の栄養のほとんどが母乳やミルクのため、食べる量が少なくても心配はいりません。緊張せず、リラックスして、ゆっくりと進めましょう
- 食物アレルギーの予防のため離乳食の開始時期を遅くしても、予防にはつながりません
- 何キログラム以上になってから離乳食を開始するといった体重による基準はありませんので、適切な月齢に開始することが大切です
くわしくはこちらから
 3.離乳食に慣れてきたら
3.離乳食に慣れてきたら
離乳食が進むと、食べられる量や種類が増え、家族の食事からの取り分けができたり、同じ献立を楽しむことができます。自分で食べたいという欲求から手づかみ食べをするようにもなります
手づかみ食べは、手と目と口の協調した運動で、十分に経験しておくとスプーンや箸などを上手に使えるようになります
くわしくはこちらから
4.離乳食の完了に向けて(1歳から1歳6か月頃)
形ある食べ物をかみつぶすことができ、栄養の大部分を食事からとれるようになります
1日3回の食事の他に「おやつ(間食)」もあげましょう
- 食事だけではとりきれない栄養素や水分を補う「軽い食事」と考えます
- おにぎりやパン、果物、乳製品などがおすすめです
くわしくはこちらから
5.離乳食から幼児食へ
離乳食が終わっても、乳歯が生えそろう3歳ころまでは調理に配慮が必要です
くわしくはこちらから

生活リズムは大人の時間に合わせるのではなく子どもの時間に合わせましょう
食事はお腹がすいたタイミングで食べられるよう時間を決めましょう
離乳食の進め方の目安

禁止食品
はちみつ、黒糖
乳児ボツリヌス症予防のために満1歳までは使わないでください
★乳児ボツリヌス症は便秘、ほ乳力の低下、元気の消失、泣き声の変化、首のすわりが悪くなる、といった症状を引き起こすことがあります。ほとんどの場合、適切な治療により治癒しますが、まれに亡くなることもあります
注意食品
牛乳
牛乳を飲用とするのは、1歳過ぎてからにしましょう
ただし、離乳食には7ヶ月頃からクリーム煮などに使えます
イオン飲料
高熱や下痢が続くときなどには、乳児用イオン飲料を使いましょう
元気な時の水分補給は、湯冷ましか麦茶で大丈夫です
上手に水分補給を使い分けましょう
衛生のポイント
赤ちゃんは細菌への抵抗力が弱いので、手指、食材、調理器具は清潔に保ちまし ょう。食材は必ず加熱し、手際よく調理しましょう
ょう。食材は必ず加熱し、手際よく調理しましょう
離乳食の保存のポイント
- 離乳食を保存する場合は食べる前に取り分ける
- 離乳食を常温で放置しない
- 冷凍したものは1週間で使い切る
- 冷凍したものは再加熱する(自然解凍はNG)
- 再冷凍はしない
体調が悪い時の離乳食
赤ちゃんの体調が悪いときは離乳食を無理に食べさせなくても大丈夫です
早めに小児科を受診しましょう
発熱
- 発汗や呼吸数が増えることで水分が多く失われるため、こまめに水分補給をします
- 水分補給には母乳やミルク、湯冷ましや麦茶が適しています
- 医師の指示があった場合には赤ちゃん用イオン飲料や経口補水液を使用しましょう
- 食欲が出てきたら、おかゆやうどん、スープなど消化の良いものをあげましょう
下痢
- 軽い下痢で機嫌がよく、食欲がある場合は離乳食の形態をひとつ前の段階に戻して様子を見ます。量はいつもより多くならないようにしましょう
- 脱水防止のため母乳やミルク、湯冷ましや麦茶など人肌程度のもので水分補給を行います
- りんごは整腸作用があるペクチンを含むため、すりおろして食べさせてあげると良いでしょう
嘔吐
- 吐き気があるときや嘔吐をしているときは、症状が落ち着くまでは絶食にします
- 嘔吐直後に水分をとると、さらに吐き気をもよおすことがあります
- 水分は吐き気が落ち着いたらあげます。スプーン1さじから少しずつ飲ませ、様子を見ながら増やしていきます
- 水分をとっても嘔吐しなくなったら、消化の良いものを少しずつあげましょう
便秘
- 便が固い、便がなかなか出ない、3日以上便が出ない、コロコロした便が出るといった場合「便秘」と言います
- 離乳食スタートによる食生活や腸内環境の変化、母乳やミルクを飲む量が減ることによる水分不足といった理由から、便秘になることもあります
- 水分補給を多くするとともに離乳食には野菜や芋などの食物繊維の多いものや、ヨーグルトや納豆(7か月以降)などの発酵食品を多く取り入れると良いでしょう
- 調理などに油やバター(7か月以降)を使うと排便が促されることもあります
防災対策
日頃から最低でも7日分程度のミルクや離乳食などを用意しましょう
普段使っているミルクやベビーフード、幼児用レトルト食品等を少し多めに用意しておき、消費期限内に食べ、使ったら補充する「ローリングストック」で、日頃の備えをしましょう

~母乳育児の方~
災害時も感染症予防等のため、母乳を続けることが勧められています。母乳が一時的に止まったり減ったように感じても、吸わせ続けることが大切です。いつもと同じ回数以下にならないよう飲ませてあげましょう
母乳があげられない状況が発生する場合を考えてミルクを準備しておきましょう
| 5-6か月 | 7-8か月 | 9-11ヶ月 | 12-18ヶ月 |
| ミルク・母乳 | おかゆ状のもので対応 | おかゆ状のもので対応 | ごはんで対応 |
食物アレルギー
食物アレルギーは、特定の食べ物を食べた時に、からだを守る「免疫」システムが過敏に働き、アレルギー反応が起こることです
自己判断せず、医師による正しい判断を受けましょう
症状
食後すぐから2時間以内に症状がでることがほとんどです
- かゆみ、じんましん、発赤(最も多い症状)
- 目の充血、かゆみ、まぶたの腫れ
- くちびる、舌の腫れ
- くしゃみ、鼻汁、鼻づまり
症状が重い場合、一つでも当てはまるときは迷わす救急車を!
- 声がかすれる、犬が吠えるような咳、ゼーゼーヒューヒューする呼吸
- 繰り返しおう吐
- くちびるや爪が青白い、血圧低下
- ぐったり、意識もうろう、尿や便を漏らす
乳幼児に多い原因食品
- 卵・牛乳・小麦

1歳児以降に多い原因食品
- 木の実類・果物類・魚卵・甲殻類・そば

離乳食の開始を遅らせても、食物アレルギーの発症を予防する効果はありません
離乳食の開始を遅らせたり制限することなく適切な時から様々な食材を少しずつ食べさせてあげて食べる楽しみを大切にしていきましょう
講習会のご案内
スタートコース
離乳食のはじめ方や進め方、作り方を講義・実習・試食やデモンストレーションを交えてお話しします
受講目安は生後4か月になる月がおすすめです
ステップアップコース
3回食への進め方や手づかみ食べの大切さについて講義・試食やデモンストレーションを交えてお話しします
受講目安は生後7か月から8か月になる月がおすすめです
パクパクコース
1歳頃からの食事・おやつについて講義・試食やデモンストレーションを交えてお話しします。
受講目安は1歳頃がおすすめです
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課のびのびすくすく担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:165、166)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ

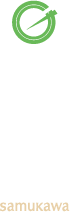


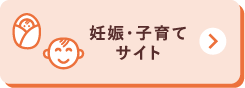
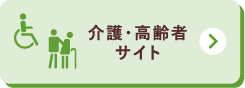





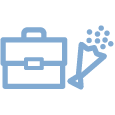





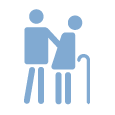

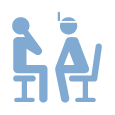



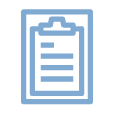

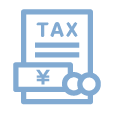

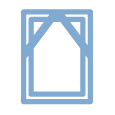

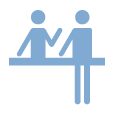



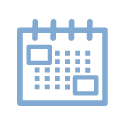





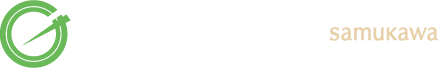
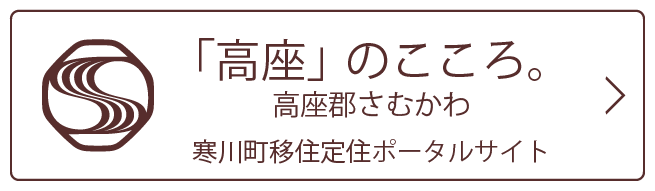
更新日:2024年04月01日