9から11か月頃(後期)の離乳食

この時期は「はいはい」や「つかまり立ち」など全身を使って活発に動くようになり、成長と活動に使うエネルギーや栄養素がますます必要になります
1日3回食の『後期の離乳食』に進めていきましょう
この時期のポイント
生活リズムを整えましょう
- 1日3回の離乳食や授乳の時間を決めると、生活リズムが整います
- 離乳食の時間の間隔は4時間以上あけましょう。また、3回目の離乳食は遅くても19時までには食べ終わるようにしましょう

固さは歯ぐきでつぶせるバナナくらいにしましょう
- 舌の動きが滑らかになり、前後、上下、左右に動くようになり、食べ物を歯ぐきに移動させ、すりつぶして食べられるようになります。歯ぐきですりつぶしやすい固さと大きさのものを用意しましょう
- 上下2本の歯が生えそろったら、前歯でかじり取る経験も増やしましょう
使える食材がさらに増えます
- おかゆは5倍がゆから軟飯が食べられるようになります
- 魚はさば、あじ、さんまなど青魚も食べていきましょう
- 肉は牛・豚のひき肉が食べられるようになります
- 少量のケチャップ、マヨネーズの調味料が使えるようになります
- 植物油やバターが使えるようになります
栄養バランスを整えましょう
これまでは母乳やミルクが栄養の中心でしたが、離乳食が3回になり離乳食の割合が高くなります
主食・主菜・副菜をそろえて栄養のバランスを整えましょう
- 主食(おかゆ・パン・麺類)
- 主菜(肉・魚・卵・大豆製品を使った料理)
- 副菜(野菜を使った料理)
不足しやすい栄養素を含む食材を積極的に取り入れましょう
鉄
- 生後6か月ころから体内の鉄分は徐々に減少していきます
- 鉄分を多く含むまぐろやかつお、牛肉や豚肉、レバーや卵黄、ほうれん草や小松菜を積極的に取り入れましょう
- ビタミンCを多く含む、じゃがいもや野菜を一緒に取ると吸収が良くなります
カルシウム
- 骨の成長に欠かせない栄養素です
- カルシウムを多く含む、小魚、乳製品、木綿豆腐や納豆、ほうれん草や小松菜などを積極的に取り入れましょう
ビタミンD
- 骨の成長に欠かせない栄養素で、カルシウムの吸収を助けます
- ビタミンDを多く含む鮭、さばやさんまなどの青魚、卵黄などを積極的に取り入れましょう
- ビタミンDは日光(紫外線)に当たることで皮膚で生成されます。適度に日光を浴びることも大切です
食べやすい環境で食べよう
からだのバランスをとりながら座ることと、食べることを一緒に行うのは難しいと言われています。体格にあった椅子とテーブルを準備してあげましょう

テーブルの高さは手がテーブルにのるくらい
- 手が自由に動かせることで自分で食べやすくなります
足は床や補助版につくように
- 足だけでなくあごにも力が入れられ、しっかりかんで食べることができます
- 椅子の高さを調節したり、クッションや厚めの雑誌などを使い足がつくようにしてあげましょう
体にあった椅子を
- 体が安定しない椅子では食事に集中するすとはできません。クッションやタオルなどで体を安定させてあげましょう
手づかみ食べの体験
大人の持っているスプーンや食べ物に手を伸ばしたりつかんだりしはじめます
止めるのではなく、たくさん経験させてあげましょう
手づかみ食べをさせる時は、窒息などの危険も伴いますので、赤ちゃんから目を離さないようにしましょう
すべての赤ちゃんが手づかみ食べに興味を示すわけではありませんので、無理強いせず、赤ちゃんに合った方法で進めていきましょう

・ 学びの行動
目で食べ物の位置や大きさ、形などを確かめ、手につかんで固さや温度、力の入れ加減などを確かめます
・ 一口量を知る
自分の手に持ち、かじり取ることによって一口量を知ることができます
・ 「自分で食べたい」気持ちの表れ
この時期自分でやりたいという欲求が芽生え始めます。手づかみ食べにより、自分で食べる楽しさを身につけていきます
・ スプーンや箸、食器を使う動きの基礎
赤ちゃんが持ちやすいおかずを準備
1品でいいので、赤ちゃんが持ちやすいおかずを用意してあげましょう
野菜をスティック状に切って軟らかく煮たり、ひき肉などを小判型に丸めたりすると手づかみメニューになります
食事中赤ちゃんの手や口を汚れるたびに拭いたり、テーブルが汚れるたびにきれいにしていませんか?
手が口が汚れることが気になり、手づかみ食べをいやがる原因につながることがあります。少しくらい汚れてもちょっとがまんしましょう
コップ飲みについて
コップ飲みの練習をステップ2へ進めましょう。口の周りの筋肉の発達にもつながります
コップ飲みの3ステップ
- ステップ1 スプーンで練習 (7から8か月頃)
- ステップ2 おちょこや小皿など小さな容器で練習(9から11か月頃)
- ステップ3 コップで練習 (1歳頃から)
ステップ2
おちょこや小皿で練習し、上手になったら底が深いお椀のような容器にステップアップしましょう
家族といっしょの食事を楽しみましょう
家族と同じものを食べることは赤ちゃんにとってうれしい体験です
離乳食の準備も、家族の食事から取り分けると楽になります
家族の食事からの取り分けポイント
- 赤ちゃんにも食べやすい食材を使って大人の食事を作ると、離乳食に取り分けやすくなります
- 野菜を多く使った汁物や煮物などが1品あると便利
- 大人もうす味を心がけましょう
家族で食べるみそ汁から離乳食を作ってみましょう
家族用のみそ汁を作る
- にんじんやじゃがいもなどお好みの野菜を2から3種類食べやすい大きさに切る
- 野菜はだし汁で柔らかくなるまで煮る
- みそを入れる
ここで離乳食用にとりわけ
- 具を取り出し、お子さんの食べられる大きさにつぶす
- 汁を3倍ほどに薄めてかける

豆腐や卵、ひき肉、魚など主菜になるものを加えると栄養たっぷりのみそ汁になります。このみそ汁とおかゆを食べれば主食、主菜、副菜のそろったバランスのいい離乳食になります
禁止食品
はちみつ、黒糖
乳児ボツリヌス症予防のために満1歳までは使わないでください
★乳児ボツリヌス症は便秘、ほ乳力の低下、元気の消失、泣き声の変化、首のすわりが悪くなる、といった症状を引き起こすことがあります。ほとんどの場合、適切な治療により治癒しますが、まれに亡くなることもあります
離乳食メニュー(9から11か月)
取り分けポイント
豆腐ハンバーグやかぼちゃのバター焼きはそのまま
みそ汁は2から3倍にお湯または出汁で薄めるてあげましょう
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課のびのびすくすく担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:165、166)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ

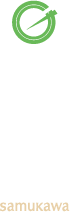


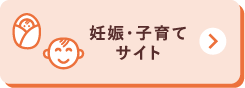
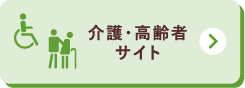





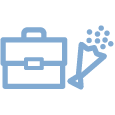





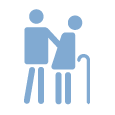

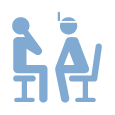



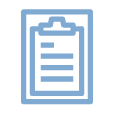

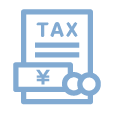

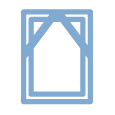

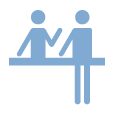



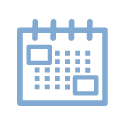





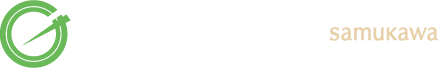
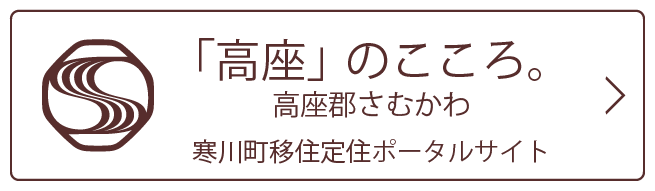

更新日:2024年04月01日