定額減税補足給付金(不足額給付金)について
給付金の概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)は、対象者の方へ早期に給付する観点から、令和5年中の所得状況に基づき給付額を算定し、給付金として支給しました。
このうち、所得税分は推計値を用いて算定したことから、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との間に差額が生じた方に対して、その差額を支給するものです。
(注意 令和6年度に実施しました当初調整給付金については、 「調整給付金(定額減税補足給付金)」のページをご確認ください。)
支給対象者
令和7年1月1日時点で寒川町に住民登録があり、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方が対象です。
【注釈】納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。
<不足額給付1>
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのち、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じる方。
【例1】
令和6年中に退職し令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方。
【例2】
令和6年中に子どもの出生等で、扶養親族等が増えたことにより、「(当初調整給付時)所得税分定額減税可能額」よりも「(不足額給付時)所得税分定額減税可能額」の方が大きくなった方。
【例3】
令和6年度分個人住民税の修正申告により、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、当初調整給付額に不足が生じる方。
【例4】
令和5年は所得がなく未申告だったが、令和6年に就職し、所得税が発生した方。
<不足額給付2>
次のすべての要件を満たす方
1. 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
2. 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者・合計所得48万円超の方)
3. 低所得世帯支援給付金(令和5年非課税等、令和6年非課税化等(注釈))対象世帯の世帯主、世帯員ではない。
【注釈】 令和5年度非課税世帯への7万円給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への10万円給付、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への10万円給付
【例1】
青色事業専従者・事業専従者
【例2】
合計所得金額が48万円超の方(医療費控除、障害者控除があり非課税となった方など)
なお、上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合(注釈)」に該当する場合があります。
【注釈】下記(1)~(3)のいずれかに該当し、低所得世帯支援給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
(1) 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
→ 所得税の定額減税対象分3万円について不足額給付2の対象となります。
(2) 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合。
→ 住民税の定額減税対象分1万円について不足額給付2の対象となります。
(3) 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
→ 所得税の定額減税対象分3万円のうち、当初調整給付の額を控除した額について不足額給付2の対象となります
定額減税可能額
所得税分=(イコール)3万円×(かける)減税対象人数
個人住民税所得割分=(イコール)1万円×(かける)減税対象人数
【注釈】
減税対象人数とは、納税者本人+(たす)控除対象配偶者+(たす)扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
支給額
<不足額給付1>
不足額給付1の支給額は次により算定します。


<不足額給付2>
不足額給付2の支給要件に該当する方に対して最大4万円【注釈】を支給します。
【注釈】令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は3万円以内
申請方法、申請時期
<不足額給付1>
・「支給のお知らせ」が届く方
不足額給付1の対象者のうち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給を本人名義の口座で受給された方には、給付内容等を記した「支給のおしらせ」を令和7年7月31日(木曜日)に発送しますので、内容を確認ください。原則、手続きは不要です。
ただし、振込口座の変更、受給を辞退される場合は、手続きが必要です。所定の様式で、提出してください。提出期限は、令和7年8月15日(金曜日)必着となりますのでご了承ください。
定額減税補足給付金(不足額給付金)支給口座変更の届出書 (PDFファイル: 110.8KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)支給口座変更の届出書 (Excelファイル: 34.1KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)支給口座変更の届出書 記入例 (PDFファイル: 116.4KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)受給辞退の届出書 (PDFファイル: 78.4KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)受給辞退の届出書 (Excelファイル: 23.8KB)
・「確認書」が届く方
不足額給付1の対象者のうち、「支給のお知らせ」以外の方に対して「定額減税補足給付金(不足額給付金)支給確認書」(以下「確認書」とする)を令和7年8月6日(水曜日)に発送します。
給付金を受け取るためには、期日までに手続きが必要です。
今回送付する「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに同封の返信用封筒に入れ、早めに返送してください。
〇確認のポイント
・「確認書」の「上記記載内容に異議ありません。」以下の欄に、必要事項(氏名、確認日、連絡先電話番号)を記載したか。
・「確認書」に振込口座等欄に口座の記載がある場合、振込口座に誤りがないか。変更を希望する場合、裏面に口座番号等を記載し、必要書類を添付したか。
・「確認書」の振込口座等欄が空欄の場合、裏面に振込を希望する口座等を記載し、必要書類を添付したか。
「確認書」の送付先の変更をご希望の方は、手続きが必要です。所定の様式で提出してください。提出期限は令和7年8月5日(木曜日)必着となりますのでご了承ください。
定額減税補足給付金(不足額給付金)支給確認書 送付先変更届 (PDFファイル: 102.6KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)支給確認書 送付先変更届 (Excelファイル: 46.5KB)
<不足額給付2>
町が把握している対象者に対して「定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書」(以下「申請書」とする)を令和7年8月6日(水曜日)に発送します。
給付金を受け取るためには、期日までに手続きが必要です。
今回送付する「申請書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに同封の返信用封筒に入れ、早めに返送してください。
〇確認のポイント
・「申請書」表面の「以下の全ての誓約・同意事項について確認し、誓約・同意します。」にチェックしたか。
・「申請書」の「1.申請者」の現住所欄に電話番号を記載したか。
・「申請書」の「本申立ての内容に相違ありません。」以下の欄に、必要事項(確認日、氏名)を記載したか。
なお、以下のような場合には支給対象者であっても、「申請書」をお送りすることができません。給付金を受け取るためにはご自身での申請が必要です。該当する方は、下記のリンクから申請書の様式をダウンロードし、指定された必要書類を同封のうえ、福祉課給付金窓口まで申請してください。
(1) 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
(2) 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合。
(3) 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書 (PDFファイル: 277.0KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書 (Excelファイル: 34.2KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書記入例 (PDFファイル: 850.2KB)
令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に寒川町に転入した方
令和6年度課税自治体における所得税等の状況把握のため、定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給確認書、支給決定通知書等の写し (令和6年に給付された当初調整給付金の額がわかる資料をご用意ください。なお、受給要件に該当せず当初調整給付金を受給していないため、上記資料をお持ちでない方は、 令和6年度個人住民税分控除不足額等がわかる資料(令和6年度分個人住民税の納税通知書、特別徴収税額通知書または(非)課税証明書)をご用意ください。
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類【注釈】とともに担当窓口へ直接または郵送にてご提出ください。
【注釈】 申請される方の状況により、必要書類が異なるため、詳しくはチラシをご参照ください。
<不足額給付1>
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書 (PDFファイル: 277.4KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書 (Excelファイル: 34.6KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書記入例 (PDFファイル: 808.6KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)不足額給付1チラシ (PDFファイル: 527.0KB)
<不足額給付2>
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書 (PDFファイル: 279.6KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書 (Excelファイル: 35.1KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)申請書記入例 (PDFファイル: 853.8KB)
定額減税補足給付金(不足額給付金)不足額給付2チラシ (PDFファイル: 481.0KB)
提出先
〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 健康福祉部福祉課給付金窓口宛
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)(必着)
給付金を装った詐欺に注意してください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
町が、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや「給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに町などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課給付金窓口
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:476、478)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ

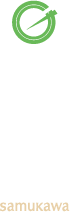


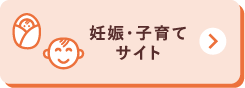
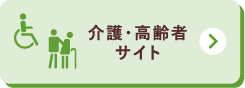





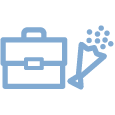





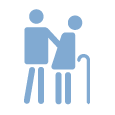

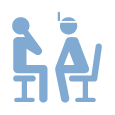



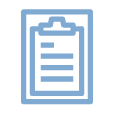

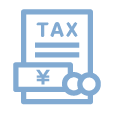

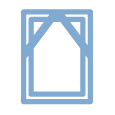

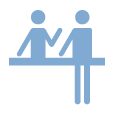



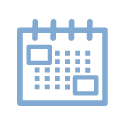





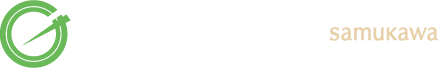
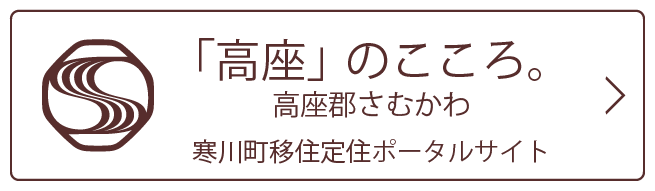
更新日:2025年07月27日