消防技術基礎訓練会を開催しました!
令和6年10月27日(日曜日)に寒川町消防団が令和6年度から開始している2年間教育の1年目に開催する消防技術基礎訓練会を開催しました。2年間教育とは、2年間を1つのサイクルとして消防団員に必要な知識や技術を身に付ける教育体制です。
火災対応訓練はもちろんのこと、大規模災害を想定した資機材取扱訓練や図上訓練、機関員や指揮者に特化した教育等、幅広い消防団業務を2年間を1サイクルとして実施するものです。1年目には火災対応の基礎的な訓練として消防技術基礎訓練会を、2年目には実際の火災現場を想定した実践的な訓練として消防技術実践訓練会を開催します。


消防技術基礎訓練会では、令和5年度に「消防団の力向上モデル事業」により全分団に配備した50ミリメートルホースとガンタイプノズルを活用し、その習熟度を確認しました。各分団は、訓練会に向けて8月から約3か月間、訓練を実施しているため、資機材の取扱は上達しており、レベルの高い訓練会となりました。
訓練会では実際の火災現場の活動を想定し、今までの消防操法訓練に主に3つの変更を行いました。1つは消防水利、消防操法では無圧水利の訓練ですが、町の消火栓の充足率を鑑み、有圧水利の消火栓を消防水利として活用する訓練としました。有圧水利の場合、ポンプを担当する機関員に小型ポンプへの負荷やその軽減、加圧の操作など今までとは違う手法が求められ貴重な経験となりました。
2つ目は防火衣を着た訓練です。消防操法では活動服での訓練となりますが、実際の火災現場では、安全管理上、防火衣、防火帽、防火手袋を身に付けることとなっています。実際の服装での活動を想定した訓練とすることで、普段とは違う服装での活動に慣れてもらうため、防火衣を着た訓練としています。
3つ目は資機材の変化です。消防操法では65ミリメートルホースと管鎗ですが、今回の訓練は現場活動用の50ミリメートルホースとガンタイプノズルを使用しました。また、二又分水器、ホースバックやトランシーバー等、実際の火災現場で使用する可能性がある資機材を訓練の中でも実際に使用することとしました。




今回の訓練の大きな収穫は「自分たちで考える」ということです。災害対応には、災害に対して自分たちができることやしなければならないこと等、様々な選択肢の中で優先順位を決め、判断し遂行していかなければなりません。
基本的な技術を身に付ける上で、決められた型を訓練することは大切なことではありますが、全てはバランスであり、自分たちで考え工夫していくことも大きな成長につながります。今回の基礎訓練会では、ある程度の枠組みとしてのルールを定めた上で、自分たちが考える部分も設定した訓練でした。団員同士が現場活動を意識した実際の活動についての考え方のすり合わせや話し合い行ったことが、災害出動が少ない中、実践的な活動を意識できる訓練になったという声もいただいております。実際、資機材の積載位置や方法など、意見交換しながら変更していった分団もあり、現場を意識した訓練となったことは大変効果の高い訓練会であったと認識しております。
令和7年度は2年間教育の2年目として実際の火災現場を想定した実践的な訓練会を行う予定ですので、消防団員の現場活動力の更なる向上を見込んでおります。


関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民安全課消防担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:465、466)
ファクス:0467-74-2833
メールフォームによるお問い合わせ

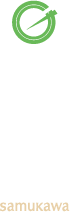


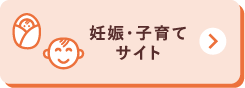
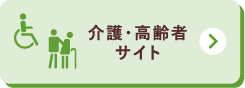





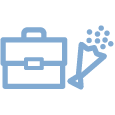





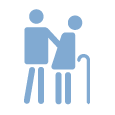

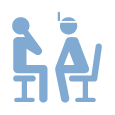



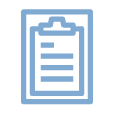

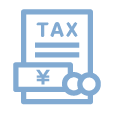

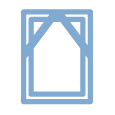

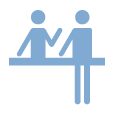



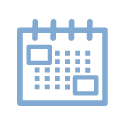





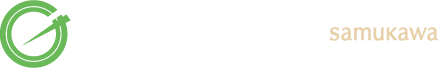
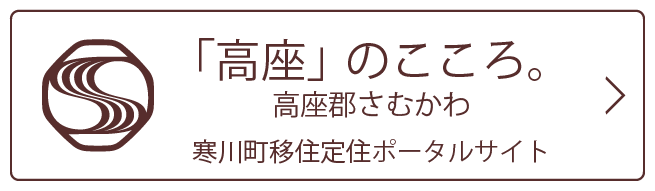
更新日:2024年11月26日