お子さんとご家族の防災知識
自然災害は、いつどこで起きるかわかりません。
自分と家族を守るために、日頃から備えておくことが大切です。
しかし、物を備えるだけが防災ではありません
妊娠中や産後の女性と乳幼児は、災害時に特別な支援が必要とされています。
しかし地域の方も支援が必要な人の存在を知らなければ、助けたくても助けることができません。
挨拶を通して地域に顔見知りを増やしたり、地域の防災訓練や防災イベントなどに参加するなど心がけましょう。
また災害時に正しく支援が受けられたり、病気の重症化や感染症の大流行を防ぐためにも、妊産婦健康診査や乳幼児健康診査、予防接種を受けておくことも大切です。
地域の防災情報を集めましょう
【情報の収集方法】
・ハザードマップの入手
・避難所の位置の確認
・町や自治会等で行われる防災訓練への参加
・防災ハンドブックの確認
わが家の防災マップを作りましょう
【作り方】
1 地図を準備する。(ハザードマップなど)
2 自宅から避難所までのルートを確認する。
(妊娠中の方や、小さなお子さんも避難できるように)
3 実際に歩いて、危険箇所を点検し、地図に書き込む。
<チェックポイント>
・古い家屋やブロック塀 ⇒ 揺れが収まった後にも倒壊の危険が。
・窪地や段差 ⇒ 洪水時には足元が見えなくなることも。
・狭い路地 ⇒ 坂道は洪水時に水の勢いが増します。
・小さな河川 ⇒ 雨量や津波の大きさによっては危険になることも。
家族の集合場所を確認しましょう
災害時に家族がばらばらになってしまったときに備えて、近くの避難所など家族が集まる場所を決めておきましょう。
・集合場所や時間を具体的に決める
例:「小学校の正面にお昼までに集合する」
・通っている保育園等の災害時の避難先・連絡方法確認、誰が迎えに行くかの分担
避難バックを見直しましょう
次にあげたものを、各ご家庭用にアレンジして準備しましょう。
【常時携行品】 緊急時に命を守るグッズは常に手元に
・緊急時の必要度が高く持ち歩けるものは、ポーチなどにまとめ、日頃から持ち歩くようにしましょう。
・母子手帳
・ホイッスル(中に玉の入っているものは濡れると音がでないのでバツ)
・携帯電話の充電器
・小型ライト(両手が使えるLEDのヘッドライトが便利)
・生理用品
・携帯トイレ
・現金
・メモ帳・ペン
・飲料水
・携帯食料
・マスク
・ポケットティッシュ、ウエットティッシュ
・ビニール袋
・紙オムツ、おしりふき
【一次持ち出し品】 「持てる・使える・助かる」が基本
・避難するときに最初に持ち出すものです。両手が使えるバッグを選びましょう。
・最優先は、命を守るグッズ。「ないと困るもの」を用意します。
次に生活必需品を選びます。
・グッズが充実していると安心ですが、重量オーバーに注意が必要です。
妊婦さんや乳幼児連れのママは5キログラムを目安に。
食料・水
・飲料水(緊急用として1人1リットル程度)
・食料(1日分程度)
避難グッズ
・懐中電灯
・ヘルメット・軍手
・スリッパ
・乾電池
・エアマット
生活・衛生用品
・非常用トイレ
・アルミブランケット
・ビニール袋
・雨具
・タオル
・衣類、下着
・洗面用具
・ハブラシ、マウスウォッシュ
・ボディーシート
医薬品・感染症対策用品
・マスク
・手指消毒液
・ハンドソープ
・ウエットティッシュ
・体温計
・絆創膏
・ガーゼ、包帯
・消毒液
・常備薬
・お薬手帳
【二次持ち出し品】 落ち着いてから取りに戻る
・避難が長引くとき、一時帰宅の安全が確認できてから持ち出すものです。
・持ち出し品リストを作り、必要度の高いものから一次持ち出し品に入れ、入りきらなかったものを二次持ち出し品に用意しましょう。
・救援物資が届くまでの間(3日間、できれば1週間)、自活できる分量を備えましょう。
食料・水
・飲料水(1人1日3リットル、1週間分が目安)
・食料(1週間分が目安)
生活・衛生用品
・非常用トイレ
・お皿・コップ・はし・やかん・鍋
・ラップ(食器にしけば汚れない)
・ドライシャンプー
・非常用給水袋
・寝袋
・カセットコンロ
・カセットコンロ用ガスボンベ(2日に1本)
・固形燃料
・耐熱性のあるポリ袋
衣類:成長や季節に合わせ必要なものを
・下着、靴下
・長袖、長ズボン
・防寒着
・毛布
・タオル、バスタオル
あると便利なもの
・新聞紙、段ボール
・携帯扇風機
・使い捨てカイロ
女性の備え
・生理用品
・サニタリーショーツ
・おりものシート
赤ちゃん、小さいお子さんの備え
自分でリュックを背負えるお子さんは、お子さん用の避難リュックを用意しましょう。
必要なものを選んで入れ、はぐれた時を想定し、お子さんの名前や連絡先を書いたカードも入れておきましょう。
・母子手帳
・オムツ、おしりふき
・お気に入りのもの(おもちゃ、絵本、タオル、ぬいぐるみ等)
・抱っこ紐
・子どもの靴
・ミルクや離乳食(「災害時に乳幼児を守るための栄養ガイド」参照)
発災時に必要な行動
洪水や土砂崩れ
・雨や河川の状況、町からの避難に関する情報を確認しましょう。
・事前にご家庭の浸水リスクを確認し、浸水の恐れがない場合は、屋内で安全確保に努めましょう。
・浸水の危険性がある場合、妊産婦・乳幼児連れの方は「警戒レベル3(高齢者等避難)」が出たら、指示に従い早めに安全な場所(安全な親戚、知人宅・広域避難場所)に避難しましょう。
地震
【発災時】
1.自分の安全を確保しましょう。身体を低くし、頭を守り、揺れがおさまるまで動かないことが重要です。
2.お子さんの頭をかばうように抱きかかえるようにしましょう。
【揺れがおさまった後】
1.割れたガラスや食器等で足を怪我しないように、靴かスリッパをはきます。
2.家の中にいる家族の安否や、被害状況を確認します。
3.ラジオ等で正しい情報を得ながら、避難バッグ等を取り出し、必要があれば避難準備をします。
【避難時】
避難時も頭を守るようにしましょう。ヘルメットがあればかぶりましょう。
妊娠後期
お腹で足元が見にくいため、できれば一人での避難を避け、段差など確認してもらうようにしましょう。
乳児
抱っこ紐やスリング等を使って、両手は使えるようにして避難しましょう。ベビーカーでは避難しないようにしましょう。
幼児
抱っこで避難する際にも靴を履かせましょう。
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課のびのびすくすく担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:165、166)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ

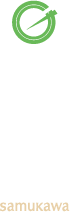


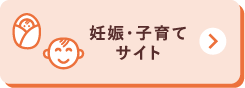
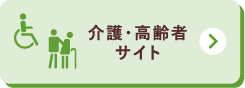





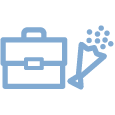





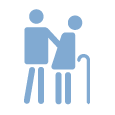

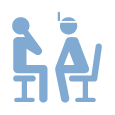



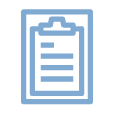

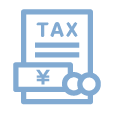

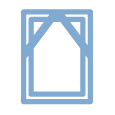

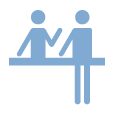



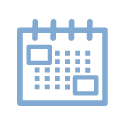





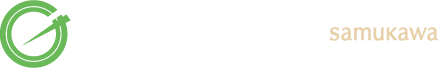
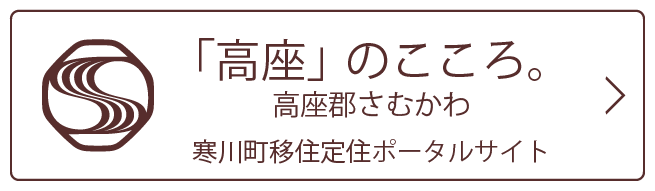
更新日:2025年09月01日