栄養士の給食コラム~献立アラカルト~
栄養士の給食コラム
このコラムでは、「献立アラカルト」として、町立5小学校で実際に食べている給食メニューのワンポイントコメントや季節の食材に関することなど、学校給食の献立に関することを随時コラム形式で掲載します。
これまでのコラムはこちらから
ありがとうの気持ちをこめて・・・ 「いただきます」「ごちそうさま」
わたしたちが元気でいられるのは、毎日食べものを食べているから。その食べものは、もとをたどれば生きものの命でした。野菜も魚もみんな生きていました。わたしたちが元気に過ごすために「食べもの」として、やってきてくれたのです。「いただきます」はその命たちに「ありがとう」の気持ちをこめた大切なあいさつです。また「ごちそうさま」は食事を作るためにかけ回ってくれた人たちへの「ありがとう」の気持ちをこめたあいさつです。
「ありがとう」の気持ちをこめたあいさつをしていきましょう。
(寒川小学校「11月こんだてひょう」より)
学校給食は栄養士が献立を考え、調理員さんが愛情をこめて給食を作ります。給食の食材は、米や野菜を作ってくれる農家さん、魚をとってくれる漁師さん、牛を育ててくれる畜産農家さんたちが、育てたりとったり作ったりした食べものを運送業者さんが学校に届けてくれます。
このように学校給食には、たくさんの人がかかわって給食を作っています。
学校給食に限らず、感謝の気持ちをもって食事をすることは大切なことですね。
自然の恵みにも感謝していただきましょう。
寒川町学校給食オリジナルキャラクター 赤兵衛 黄々丸 お緑
食べ物はいろいろな食品でできています。食品は、その中に含まれる栄養素の体内での主な働きにより3つのグループに分けられます。
寒川町の学校給食では、3つのグループにオリジナルキャラクターを作成し食育を推進しています。
主に体をつくるもとになるもの →赤グループ 赤兵衛
主にエネルギーのもとになるもの→黄グループ 黄々丸
主に体の調子を整えるもの →緑グループ お緑




5月からは、各ご家庭に配布する献立表に「寒川の日」というマークを付けました。

「寒川の日」マーク
児童生徒には、食材が身近な畑で育っていることを感じながら給食を食べてほしいと考えています。旬の野菜の栄養についても知らせています。(献立表は町のホームページからもご覧いただけます。)
≪寒川産の野菜が育つ畑を見学しました≫
JAさがみにご協力をいただき、以前にも実施した町内の農家の畑見学を7・8月に行いました。給食の調理がないので午前中の時間をたっぷり使って、貴重なお話を聞く事ができました。学校での食育や、給食センターで行っている試食会での話題などに活用しています。
なす・青パパイア・さやいんげんなどの栽培 (小動の脇さん)
少量多品種の野菜を栽培してわいわい市や市場にも出荷している脇さんの畑では、つやつやしたなすや、めずらしい青パパイア、さやいんげん、寒川町では脇さんだけが栽培しているという緑色のなすなどを拝見しました。夏の日差しの中で元気に育つ野菜の数々がおいしそうで、ぜひ児童・生徒にも食べてもらいたいと感じました。さやいんげんは市場に出荷しているとのことで、給食でも使わせてもらいたいとお願いしてきました。また、青パパイアは、10月に給食用として納品してくれました。

緑色のなすと脇さん

脇さんのなす

脇さんの青パパイアの木
長ねぎ・ゴーヤなどの栽培(小谷の関口さん)
岡田地区に300坪(約1000平米)の畑で長ねぎを3万本育てている関口さん、主に町内のスーパーに出荷しています。9月に入ってからは給食用にも納品してくれていて、年間を通して出荷ができるように栽培をしています。
他の畑でも7万本の作付けをしています。秋から冬にかけて、収穫時期をずらしながら栽培します。植え付けや土をよせる作業は機械を利用して、たくさんの量を栽培できるように工夫しています。
また、新しい栽培方式としてトンネルでナスやトマト、ゴーヤを栽培しています。これは、「子どもたちに、野菜を「食べる」だけではなく、「栽培」の楽しさを体験してもらいたい」との思いから始めたものです。
畑の一角に作っているゴーヤのトンネルは、収穫体験に来た人のための日よけ用も兼ねて育てているとのこと。涼しい風が吹きぬけてホッとできました。
9月に入ってから給食用に長ねぎを納品してくれました。いつも畑から運んだ長ねぎの皮をむいてきれいに整えてくれている奥さんと二人で納品に来てくれました。

関口さんのネギの納品

関口さんのネギ畑

関口さんのゴーヤのトンネル
児童・生徒が楽しみにしている夏休み、給食のない期間の給食センターでは、機械類のメンテナンス・普段できない高所の清掃、調理エリアの消毒などを行いました。
職員は、衛生管理・調理機器の研修会を受講し、よりよい給食づくりに役立つよう知識と技術の向上に取り組みました。
取り組みの中では、野菜のおいしさをより活かすことができる調理方法の研究や、魚をおいしく提供する調理方法の研究などを通じて、今後の給食献立に活かしていこうと考えています。
加えて栄養士・栄養教諭は、上記の研修会の準備や資料作成、調理員と打ち合わせを行うほか、食育に関する研修を受講したり、3学期や来年度の献立の計画立案をしたりして集中的に仕事を進めました。




また、YouTubeに配信して好評な「おうちで給食」の第2弾について動画撮影を行いました。
人気のある献立の作り方が後日追加で配信されますので楽しみにしていてください。広報戦略課の協力を得て公開の準備を進めています。調理員が調理方法を実演する様子をご覧いただけると思います。
町内の農家の皆さんから協力いただいている地場野菜、6月にはミニトマトやきゅうりなどの夏野菜が加わり、7品種を給食に使う事が出来ました。
こんな料理に使いました!
| 月 | 日 | 曜日 | 料理 | 生産者 | 食材 | 量 |
| 6月 | 5日 | 水曜日 | のり酢和え | 田端の石黒さん | 小松菜 | 88キログラム |
| 5日 | 水曜日 | キムチ入り肉豆腐 | 田端の高橋さん | たまねぎ | 18キログラム | |
| 7日 | 金曜日 | ごまドレッシングサラダ | 小谷の大久保さん | きゅうり | 18キログラム | |
| 11日 | 火曜日 | ミニトマト | 大蔵の菊池さん | ミニトマト | 135キログラム(約7700個) | |
| 12日 | 水曜日 | 豚肉と厚揚げの中華炒め | 宮山の小菅さん | 長ねぎ | 19キログラム | |
| 19日 | 水曜日 | 沖縄みそ汁 | 小谷の馬谷原さん | たまねき | 33キログラム | |
| 20日 | 木曜日 | キムチスープ | 宮山の小菅さん | 長ねぎ | 31キログラム | |
| 25日 | 火曜日 | かきたま汁 | 小動の福岡さん | ほうれん草 | 48キログラム | |
| 27日 | 木曜日 | おひたし | 一之宮の鈴木さん | キャベツ | 77キログラム | |
| 27日 | 木曜日 | おひたし | 小動の福岡さん | 小松菜 |
77キログラム |
|
| 7月 | 1日 | 月曜日 | ABCスープ | 一之宮の鈴木さん | キャベツ | 79キログラム |
| 5日 | 金曜日 | 星のハンバーグトマトソース | 小谷の関口さん | たまねぎ | 60キログラム | |
| 8日 | 月曜日 | フレンチサラダ | 小谷の大久保さん | きゅうり | 16キログラム | |
| 12日 | 金曜日 | 夏野菜のラタトゥイユ | 小谷の馬谷原さん | なす | 48キログラム |
《寒川産の野菜が育つ畑を見学しました》
ほうれん草・小松菜のハウス栽培(小動の福岡さん)

7つのハウスでほうれん草や小松菜を主に栽培する福岡さん。わいわい市や市場に出荷しています。小松菜は約22日、ほうれん草は30日ほど、冬には45日以上育ててから出荷します。炭を砕いて土にまぜたりしてよい土を作り、おいしくて丈夫な野菜を育てています。


きゅうり・なすなど、夏野菜の露地栽培(小谷の大久保さん)



主にわいわい市に出荷するために、年間40種類以上の野菜を栽培しています。様々な野菜の栽培方法に詳しい大久保さんは、新しく農業を始める人の先生もしています。よりおいしく、珍しい野菜の栽培にも挑戦しています。黒い色のピーマンがなっていたり、空中に育つかぼちゃについて、珍しいきゅうりの栽培についてなども教えていただきました。
学校給食センターでは昨年9月に開所して以来、寒川町で育った野菜を使用した給食づくりを進めています。以前から地産地消を意識した献立作りをしていましたが、JAを通して生産者の方々が直接届けてくれる野菜はとてもおいしく、給食をさらにおいしくしてくれています。今年度はHPの栄養士コラムで給食での使用状況をお知らせしていきたいと思います。
寒川産の野菜を使用する日は、HPでお知らせする「献立の配食例」とともに、トピックスを作成してお知らせをしています。
こんな料理に使いました!
| 月 | 日 | 曜日 | 料理 | 生産者 | 食材 | 量 |
| 4月 | 16日 | 火曜日 | 豚肉と厚揚げの中華炒め | 小谷の関口さん | 長ねぎ | 24キログラム |
| 30日 | 火曜日 | きのこのみそ汁 | 宮山の金子さん | 生しいたけ | 17キログラム | |
| 5月 | 2日 | 木曜日 | 豚汁 | 小谷の脇さん | 長ねぎ | 25キログラム |
| 9日 | 木曜日 | ビビンバ | 小動の福岡さん | 小松菜 | 75キログラム | |
| 14日 | 火曜日 | ごま酢和え | 田端の石黒さん | 小松菜 | 51キログラム | |
| 15日 | 水曜日 | わかめと卵のスープ | 小谷の関口さん | 長ねぎ | 25キログラム | |
| 16日 | 木曜日 | 大根と青菜のスープ | 宮山の小菅さん | 長ねぎ | 25キログラム | |
| 16日 | 木曜日 | 大根と青菜のスープ | 田端の石黒さん | 小松菜 | 69キログラム | |
| 20日 | 月曜日 | 春雨みそスープ | 小動の福岡さん | ほうれん草 | 49キログラム | |
| 23日 | 木曜日 | チゲスープ | 田端の高橋さん | たまねぎ | 66キログラム | |
| 24日 | 金曜日 | サンマー麺 | 宮山の小菅さん | 長ねぎ | 24キログラム | |
| 24日 | 金曜日 | サンマー麺 | 田端の高橋さん | たまねぎ | 44キログラム | |
| 28日 | 火曜日 | かきたま汁 | 田端の石黒さん | 小松菜 | 51キログラム |

田端の石黒さんの小松菜です。5月14日に51キログラム、5月16日に69キログラム、5月28日に51キログラムの小松菜が納品されました。

たくさんの新鮮な小松菜を納品時丁寧に農家さんと検品し、「ごま酢和え」「大根と青菜のスープ」「かきたま汁」などのおいしい給食になっています。
≪衛生に気を付けよう≫
梅雨明けが待ち遠しいこの頃、湿度や気温が高くなり、細菌が繁殖しやすい状態が続いています。食中毒が増えてくる傾向があるので、食品や調理器具の取り扱いに注意したいですね。今回は食中毒を防ぐポイントをお知らせします。
食中毒を防ぐ3つのポイント
つけない
〇手を洗い、野菜などの食材や調理器具などをきれいに洗う。
〇生の食品(肉など)にふれた手やはしから調理済みの食品に細菌などが移らないようにする。
増やさない
〇買い物から帰ったら、細菌などが増えないように、すぐに食品を冷蔵庫にいれる。
生ものや料理はできるだけ早く食べる。
やっつける(加熱する)
〇ほとんどの細菌やウイルスは熱に弱いので、食品は中まで火が通るように加熱する。75℃で1分以上がめやす。(二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は85~90℃で90秒以上)
注意:食中毒菌の中には、「熱に強い殻(芽胞)を作る」という特徴を持った種類の菌もいます。その特徴を持つ、セレウス菌、ウエルシュ菌などは、調理した食品はすぐ食べる、加熱後の食品を保管する場合は粗熱をとり冷蔵(10℃以下)で保管することが大切です。
文部科学省 小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」一部抜粋
【手洗いクイズ】
たくさんの食事を作る給食調理員は、衛生管理に注意して毎日の給食を作っています。手洗いも爪ブラシを使ったり、二度洗いをしたりしてきれいな手で調理をしています。プロの調理員でも洗い残しが多いので、特に注意して洗っているところはどこでしょうか?
七夕
七夕は、彦星と織姫が天の川をはさんで別れ別れになり、一年に一度だけ会うことをゆるされたという中国の伝説から生まれた行事です。七夕には願い事を書いた短冊などを笹竹に飾り、行事食のそうめんを食べる習慣が伝わっています。
町内の各学校の給食では、
「天の川スープ」「七夕そうめん汁」「星のハンバーグトマトソースかけ」などとともに、「きらきらもち」「七夕ゼリー」「フルーツミックス」など、子どもたちに人気がある冷たいデザートも登場します。
【食べ物ものしりクイズ】
夏の暑いときには冷たい「そうめん」や「ひやむぎ」がおいしいですね。見た目はよく似ているそうめんとひやむぎですが、その違いはどこでしょうか?
≪夏野菜 トマト≫
これから梅雨に突入する6月は、雨でジトジトした日が続き、食欲も減退しますね。しかし6月は、夏野菜が出回る時期でもあります。夏野菜には疲労回復や食欲増進などの作用を持つ栄養成分が含まれています。夏の野菜を積極的に活用し、調理方法を工夫して、食欲が落ちないようにしたいですね。
今では一年中手に入る野菜ですが、最も適した時期に育った野菜は、新鮮で、栄養価が充実していて、値段も手頃なのが魅力です。たとえばトマトは、リコピンとう赤色色素の含有量を比べると、夏は冬の約3倍も多いことがわかっています。トマトは世界中で食べられていて、数えられないくらい何千種類とあるようです。生で食べても、加工してもおいしいトマト。学校給食でも5月から寒川産のトマトが登場しています。今回は、トマトの豆知識を紹介します。
トマトはナスやジャガイモの親戚です
トマトは、ナスやジャガイモと同じナス科ナス属の植物です。トマトの故郷は南米のアンデス高原とされています。時期や手段は不明ですが中央アメリカのメキシコに伝わり、そこで食用として栽培されるようになりました。ちなみに「トマト」という呼び名は、メキシコ先住民の言葉,ナワトル語の「トマトゥル」が由来と言われています。
トマトの赤はリコピンの赤
トマトは美肌効果のあるビタミンC、老化を抑制するビタミンĒが豊富で、ミネラルや食物繊維などをバランスよく含んでいます。そして赤色の色素成分で抗酸化作用があるリコピン(リコペン)がたくさん含まれています。リコピンは熱に強く、脂肪性なので、油を使って加熱調理することで効率よく摂取することができます。トマトは他の野菜に比べて一度にたくさん食べられるのがうれしいですね。ヨーロッパでは「トマトが赤くなると医者が青くなる」とうことわざがあるほど、健康によい野菜です。
日本に伝わったのは江戸時代
日本にトマトが伝わったのは17世紀のなかば、江戸時代とされています。しかし、最初は食べ物でなく「珍しい形の鑑賞用植物」だったそうです。トマトを食べるようになったのは、明治時代になってから。それ以降日本でも生産されるようになりました。
(農林水産省ホームページより一部抜粋)
【食べ物栄養クイズ】
トマトの名前の由来、古代メキシコ語の「トマトゥル」とは、どんな意味でしょうか?
正解だと思うものをタッチしてみて!
朝ごはんを食べて元気にスタート!
新年度が始まって、もう1ヶ月半が過ぎました。若葉が美しく、吹く風もさわやかですごしやすい季節ですね。新しい環境に慣れた一方で、ゴールデンウィーク明けの疲れが残っている人もまだいるようです。大人も子供も疲れが出やすい時期ですが、学校がある日だけでなく、休みの日にも早寝・早起きを心がけ、朝ごはんをしっかり食べることで、自然と体調が整ってきます。学習も運動もベストな状態で取り組めるように工夫してみましょう。
生活のリズムを整えるには、朝ごはんをしっかり食べることが大切です。私たちの体は寝ている間にもエネルギーを使っているので、朝起きた時には体の中のエネルギーは少なくなっています。朝ごはんは眠っていた脳や体を目覚めさせ、午前中に勉強したり運動したりするエネルギーの素になります。
また、朝ごはんに摂取したたんぱく質を原料として、睡眠をうながすホルモンのメラトニンが作られることが分かってきました。朝ごはんが夜の睡眠にかかわっているなんて、驚きますね。
【食べ物栄養クイズ】
朝ごはんでよく食べる料理です。メラトニンの原料、たんぱく質を多く含むのはどれかな?
ヒント:たんぱく質が多いのは、「赤のグループ」赤兵衛がおすすめする食べ物です。
正解だと思うものをタッチしてみて!!

こどもの日(端午の節句)
5月5日は、国民の祝日「こどもの日」です。こどもの日は男女関係なく「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日とされています。1948年(昭和23年)に制定されました。
また、中国から菖蒲などの薬草を厄除けにする習慣が伝わり、古くから宮中の行事に取り入れられていました。鎌倉時代ころから男子の成長を祝い、武者人形を飾ったりする「端午の節句」となりました。
令和の世になっても、初夏の風に泳ぐ鯉のぼりを見ることができますね。家庭では武者人形を飾り、菖蒲の葉や根を入れた菖蒲湯につかって邪気を払う行事が伝わっています。そして、かしわ餅やちまきは、季節感のあるお菓子として欠かせない存在ですね。
かしわ餅は関東地方でよく食べられている端午の節句のお菓子です。かしわの葉は新芽が出るまでは葉が落ちないことから、家系が絶えないという縁起物として江戸時代から伝わっています。一方ちまきは中国から作り方が伝わったお菓子で、茅の葉や笹の葉でもち米やもち菓子を包んで蒸したものです。全国各地で葉の種類や形が異なるちまきが作られています。
給食では、5日ではありませんが、こしあん入りの白い餅を、生のかしわの葉で包んで蒸しあげた定番のかしわ餅で児童の成長をお祝いします。
春の訪れを感じさせるたけのこ。たけのこは、成長が速く、すぐに竹になってしまうため、生のたけのこを楽しむことができるのは限られた期間です。国内で食べるたけのことして一般的なモウソウチクのたけのこは、3月から5月にかけての時期が旬です。たけのこ掘りをされた方もいるのではないでしょうか? 竹に旬と書いて「筍」という字になりますね。「筍」という字は、一旬(いちじゅん、10日間)で竹になることが由来といわれています。「雨後の筍」という言葉が示すように、条件が整うと次々に伸び始め、1日に121センチメートルという記録もあるそうです。
たけのこは、独特の香りと味、そして歯応えが特徴です。たけのこはさまざまな料理の食材として活躍します。また、食物繊維が豊富で腸内環境を整えるとともに、コレステロールの吸収を抑える働きや塩分の排出を促すカリウムを多く含むなど、動脈硬化や高血圧の予防も期待できるといわれています。
たけのこは、炊き込みご飯や煮物、和え物、揚げ物、炒め物など幅広い料理で楽しむことができます。給食でも「たけのこごはん」や「煮物」に登場します。この時季しか味わえない旬のたけのこで春を感じてみましょう。
(農林水産省ホームページより一部抜粋)
たけのこクイズ
問題 私たちが普段食べている野菜や果物は、花(つぼみ)・葉・果実や種子・茎・根などの植物の一部を食べています。春においしいたけのこは、竹のどの部分を食べているのでしょう?
正解だと思うものをタッチしてみて!!
新年度が始まりました。新しい先生、新しいお友達、新しい教室。ワクワクしている様子がよくわかります。ワクワクすることは、もうひとつ増えますね。
2~6年生は4月10日月曜日から、1年生は18日火曜日から給食が始まります。
学校給食は、教育活動の一環として実施されています。学校給食の目標は、1回目栄養士コラムに記載してありますので、ぜひ一度時間がある時に見直してみていただければと思います。
今年度の小学校での学校給食は、1年間184回の予定です。1年間365日、1日3回の食事を考えれば、学校給食は1年間の6分の1の回数しかありません。6分の5は家庭での食事となります。子どもたちが心もからだも大きく成長するため、また自身の健康を守っていくために、家庭・地域・学校が協力して子どもたちの食について考えていきたいと思います。
給食場のスタッフも給食を楽しみにしている児童の期待にこたえられるように、安心・安全でおいしい給食をめざします。また、今年度は2学期より学校給食センターでの給食も始まります。1学期は学校給食場での最後の給食になります。おいしく、楽しい思い出の残る給食作りにも頑張りたいと思います。
中学生の皆さんは、2学期からの給食を楽しみにしていてください。
今年度も学校給食での情報をお伝えしていこうと思います。
栄養士コラムどうぞよろしくお願いします。
来年度9月から給食センターが完成し、町内の小学校・中学校すべての給食を調理するようになります。未経験な規模の大量調理となりますが、最新鋭の機械や衛生管理に配慮された施設を使いこなして、安心・安全でおいしい給食を作りたいと考えています。
給食センターでの給食づくりに向けて栄養士・調理員はすでにシミュレーションを重ねています。教育委員会の担当者は小・中学校の先生方と連絡を密にとって、安全に配慮した施設の改修を行ったり、事務内容の整備をしたり、公会計の準備も進めています。
また、給食センターの取り組みの柱の一つ、地産地消を意識した給食づくりのために、町内の農家の皆さんやJAの方々にご協力をいただいて、町内産の野菜を先行して小学校給食で使い始めました。農家の皆さんの技術力の高さと収穫後すぐに使用できる格別の新鮮さで、素材の味を楽しめる給食となっています。各学校の栄養士からは「地元にこんなにおいしい野菜があることを知ることができた。」「ぜひ子どもたちにたくさん食べてもらいたいと思った。」という声が届いています。自然条件に左右される不安定さはありますが、町内の様々な野菜を、工夫をしながらおいしくいただきたいと思います。
現在の小学校での給食づくりは7月までとなります。長い期間使い慣れた給食場に名残を惜しみながら、いままで培ってきた給食づくりを新しい給食センターにつないでいく取り組みの様子を、栄養士コラムでもお伝えしていきたいと思っています。
11月から始めたコラムですが、まだまだ手探りで書きすすめています。ついつい長文になりがちですが、多くの方が最後まで読んでくださり、とてもありがたいです。新年度以降もよろしくお願いいたします。
今年度の給食も後わずかとなりました。学校は1年間のまとめの時期になり、給食についても、よく噛んで食べたかな? 食べられる量は増えたかな? 好き嫌いは減ったかな? 箸の持ち方は上手になったかな? 給食当番をみんなと協力してできたかな?など、1年間の振り返りを行います。無理をしなくても1年生から6年生になって卒業するまで、食に関する体験を重ねることで、ゆっくりと身につけられるといいですね。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で衛生管理の注意点が多く、黙食で過ごした給食時間ですが、子どもたちの心の中に『楽しくておいしかった給食』として記憶してもらえたら嬉しく思います。
卒業をひかえた6年生に「もう一度食べたい給食」のアンケートをとった学校や、委員会活動などで「給食の献立を考えよう」と献立作成に取り組んだ学校もあり、2月ごろから各学校の給食の献立として実施されています。
6年生になると、家庭科や給食で学んだ知識や普段の食事を参考にしながら、給食の献立を考えることができるようになっています。実際の給食に出す、全校児童が食べる献立を6年生が考える機会があります。「やりがいがある」と夢中で考えてくれて、最上級生はとても頼もしいです。
印象に残っている給食や、自分たちで考えた給食を食べたりすることで、より食べることに興味を持ち、食事の選び方や栄養のバランスについても知ってほしいと考えています。
ひなまつり(桃の節句)
ひなまつりは、中国から伝わった行事が起源となっています。川に入って身を清めたり、紙で作った人形を流して邪気を払ったりする習慣「流し雛」が、宮中の貴族の行事などつながって庶民にも広まりました。江戸時代頃からひな人形を飾る風習に変わり、女の子の健やかな成長を願う現在のひなまつりとなりました。
ひなまつりの行事食といえば、ちらし寿司、菱餅、ひなあられなどがありますね。他にもひな壇にかざる干菓子や、生菓子のよもぎ餅や桜餅、ひなまつりをイメージしたケーキなど、子どもたちが喜ぶ食べ物がたくさんあります。
「ちらし寿司」は、ひなまつりに限らずお祭りのときなどにも食べられています。長寿を意味するエビや、先を見通せるというハスなどの縁起の良い食べ物を使い、にんじんを花形にしたりして、錦糸卵、桜でんぶ、きぬさやなどで華やかに盛り合わせてひな祭りのお膳を彩ります。
「菱餅」の三色の色は、白い雪のつもった大地から緑の芽が出て桃の花が咲くという春の始まりの様子をあらわしていると言われています。菱餅の形は、菱の実の形に似せていて、鬼を追い払う力があると信じられています。
「ひなあられ」は、菱餅を小さく切ってあられにしたものですので、菱餅の三つの色が基本になっています。甘い関東風に対して、塩やしょうゆで味をつけた関西風の味付けもあります。
3月の給食では、五目寿司・こんこん寿司・牛肉寿司・手巻き寿司・カラフル丼など、各学校が工夫した献立を実施します。デザートには、ひな菓子(ひなあられ)・さくら餅・ひし餅・三色花ゼリーなどが予定されています。各教室で楽しいひなまつりが出来るといいですね。
<牛乳のはなし> 
給食では牛乳が毎日のようにでています。栄養のグループでは、「血や肉や骨をつくる赤のグループ」です。オリジナルキャラクターの「赤兵衛」が、忍法ぐんぐんの術で「みんなのからだを成長させるよ」と児童にお知らせしています。
牛乳の栄養といえばカルシウムが多いことで知られていますね。体への吸収率も他の食品に比べて高く、カルシウムの他にも成長に必要な様々な栄養素が多く含まれています。給食の牛乳1本で1日に必要なカルシウムの約4分の1をとることができます。
体が大きく成長する小学生は大人と同じ量のカルシウムが必要ですし、中学生は一生のうちで一番多くのカルシウムが必要とされています。(日本人の食事摂取基準 2020年版)
寒い季節には冷たい牛乳は飲みにくいですが、ホットミルクにしたり、シチューなどの料理に使ったり、牛乳から作ったチーズやヨーグルトなどからも牛乳のカルシウムを摂取することができます。
2月の給食では、ホタテのチャウダー・コーンシチュー・グラタン・クリームスパゲティなどに牛乳やチーズ、生クリームなどの乳製品を使用します。

文部科学省 小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」より
節分
今年の節分は2月3日です。節分は、もともと立春、立夏、立秋、立冬の前日のことでしたが、今では立春の前日のことだけをいうようになりました。節分の日に「いり豆」を歳の数や歳にひとつ足した数を食べると一年を元気に過ごすことができるといわれています。
最近では節分行事の食べ物として定着しているのが「恵方巻」ですね。
給食では、2月3日には「福豆」が登場します。福豆を食べて一年元気に過ごしたいですね。
食べ物の栄養 <大豆のはなし>
大豆は「畑の肉」とも言われるほど、たんぱく質量が豊富な食べ物です。しかも、大豆のたんぱく質は体内で作ることができない必須アミノ酸9種類を含め、人間が必要とするアミノ酸20種類すべてを含んでいる栄養価が高い食品です。
日本では弥生時代から栽培されていて、昔から日本各地の生活の中で利用されてきた大切な食べ物です。さまざまな食品や調味料に加工して食べられていますが、中でも、みそ、しょうゆ、豆腐は和食には欠かせない食べ物です。ほかにも大豆を加工してできる食べ物は、たくさんあります。お店でも売っているので、探してみてください。
給食でも2月は「豆料理」がたくさん登場します。楽しみにしていてください。

文部科学省 小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」より
全国学校給食週間
毎年1月24日~30日の「全国学校給食週間」です。
学校給食の歴史は、明治22(1889)年に山形県にある小学校で、貧しい子どもたちへ昼食を無料で提供したのが始まりとされています。その後、日本各地で給食が実施されるようになりました。しかし、戦争が始まり食料不足で給食が中断されてしまいました。戦後、支援物資により給食が再開され、これを記念して「全国学校給食週間」が設定されました。
現在の学校給食は、児童生徒に栄養バランスのとれた食事を提供するだけでなく、郷土食や行事食、地産地消の給食、また世界の多様な食文化への理解を深めるため、さまざまな国の料理も取り入れています。毎日の給食をとおして、栄養バランス、食文化、食べものへの感謝の気持ちなど、さまざまなことを学ぶために給食を「生きた教材」として活用し食育を推進しています。
寒川町の学校給食でも「学校給食週間」には、日本の郷土料理やさまざまな国の料理,をお届けします。
【各学校の献立例】
「サンマーめん」 横浜発祥
「ぬっぺ汁」 長崎県郷土料理
「すいとんじる」「手作りお好み焼き」 寒川産の小麦粉を使用
「大学芋」 児童が育てたさつまいもを使用
「まっちゃあげパン」 あげパンは東京学校給食発祥
「パエリア」「オイロサルダ」 スペイン料理
「アイントプフ」 ドイツのスープ
「チゲなべスープ」「チャプチェ」 韓国料理
他にも「給食委員会が選んだ思い出の献立」や「調理員さんリクエストメニュー」が登場します。
「全国学校給食週間」には、ぜひご家庭でも学校給食を話題にしていただければと思います。
明けましておめでとうございます。
年末年始には地域で昔から行われている祭りなどの行事がたくさんあります。このような行事には、その季節にあったごちそう(行事食)があり、それぞれに意味が込められています。わたしたちの生活にかかわる行事を大切にし、行事食を楽しみたいですね。
1月の行事食は、「おせち料理」「雑煮」「七草がゆ」「鏡開き・お汁粉」「小正月・小豆粥」などがあります。
鏡開きは1月11日です。この日は、正月に供えていた鏡餅を木づきなどで割って食べて無病息災を願います。「割る」や「切る」は縁起が悪いため「開く」という言葉が使われます。鏡開きのお餅は、お汁粉や雑煮にして食べることが多いです。
給食では、鏡開きにちなんで「おしるこ」「あんこもち」などが登場します。
楽しみにしていてください。
〈冬至・クリスマス〉
学校給食では、季節ごとの行事食を取り入れて献立を作成しています。栄養バランスとともに、伝統的な食文化や食べる楽しみも給食で味わってほしいと思います。
冬至は、1年のうちで最も昼(日の出から日没まで)の時間が短く、夜が長い日です。昔から冬至には、ゆず湯に入り、かぼちゃや小豆を食べると、健康に過ごせるという言い伝えがあります。栄養的にみてもかぼちゃはビタミンAの素になるカロテンが豊富ですし、小豆は不足しやすい食物せんいや鉄が豊富な食べ物です。冬至の日に限らず寒さが厳しくなる季節に食べて、風邪にまけない強いからだをつくりたいですね。
12月の給食では、かぼちゃを使って、「ほうとう」や「パンプキングラタン」「(かぼちゃいり)カレーライス」を作る学校があります。
冬休みに入る前、2学期の給食最終日は各学校とも「おたのしみ給食」です。内容は当日まで秘密ですが、毎年人気がある献立なので児童もワクワクしていることでしょう。栄養士、調理員からの心を込めたクリスマスプレセント「おたのしみ給食」を味わってほしいです。
≪新米≫
寒川町の学校給食は、一週間に3回給食場でごはんを炊いています。
秋に実ったお米のことを「新米」といいます。新米は水分が多く甘みや粘りが強く、香りがよいのが特徴です。米は日本人の主食であり、私たちの食生活をささえている大切な食べ物です。ごはんは和食はもちろん、洋食、中華などどんなおかずにもあいますね。
ダイエットのためにごはんを控える大人がいますが、成長期の児童にしっかりと食べてほしい、1回の食事に欠かすことができない主食です。
給食で使用する米は、年間を通して神奈川県内産が主体となっています。現在は、令和4年度産の神奈川県産「新米」が納品されています。寒川産の米も納品されることがあります。
栄養のグループでは、「主にエネルギーのもとになる黄色のグループ」で、オリジナルキャラクター「黄々丸」が忍法ポカポカの術「エネルギーみなぎるぞー」っと気合を入れて主食の大切さを児童にアピールしています。
≪きのこ類≫
学校給食の栄養のグループ分けでは「緑グループ」になるきのこ類は、菌類で、野菜とは違う食品です。栄養面では低カロリーで、不足しがちな食物繊維、カルシウムの吸収を助けるビタミンDが多く含まれています。また、免疫機能を高めるβ-グルカンという成分も豊富に含まれます。
天然のきのこは秋が旬ですが、市場に広く出回っているのは菌床栽培という栽培方法で育てたきのこです。寒川町内でも生しいたけが栽培され、10月から5月頃まで出荷されています。
11月の給食には様々なきのこ類を使った献立が登場しています。
生しいたけ・・・・『「高座」のこころ。』鍋・けんちん汁
干ししいたけ・・・麻婆豆腐・みそしる・筑前煮・トックのスープ・春巻き・酢豚
エリンギ・・・・・わかめのさっぱりあえ・中華炒め
まいたけ・・・・・秋のカレーライス・炒めスパゲティ・きりたんぽ鍋
えのきだけ・・・・秋のカレーライス・秋のクリームスープ・わかめスープ
なめこ・・・・・・なめこ汁・かみなり汁
きくらげ・・・・・チャンポン・サンマーメン・中華炒め
マッシュルーム・・ハンバーグトマトソース・秋のクリームスープ
しめじ・・・・・・鮭のちゃんちゃん焼き・さつま汁・秋のカレーライス・グラタン
≪鮭(サケ)≫
食卓によく登場する鮭は、給食でもおなじみの魚です。魚が苦手という児童もいますが、食べなれている鮭は、抵抗なく食べることができる児童が多いようです。
11月の献立だけでも、シンプルな「鮭の塩焼き」の他、「鮭のちゃんちゃん焼き」「鮭の香味だれ」「秋鮭のハーブ焼き」「鮭まぜごはん」と、様々な献立になっています。
川で生まれて海に下り、数年かけて成長し、生まれた川に戻って産卵する鮭は資源保護のため、稚魚を放流したり漁獲量の制限をしたりしています。近年では養殖した鮭も流通しています。
3つのグループの中では「赤のグループ」で、たんぱく質が豊富、ぐんぐん成長する児童の体を作る食べ物です。
現在、町では「穏やかさ、優しさ、あたたかさ」といった寒川らしさを大切にする『「高座」のこころ。』というブランドスローガンを掲げています。
町立の小学校5校の給食で11月の前半に『「高座」のこころ。』鍋が新登場します。11月1日の町制記念日にちなんで、町内で生産された野菜や小麦粉を使った鍋料理を作ります。
「高座」のこころ。鍋は、主な食材に、寒川産品や神奈川県内産品を使用し、身近で、かつ、生産者が分かることで寒川を感じながら、より一層の安心できる給食を楽しんで欲しい、給食をきっかけに、寒川町について興味や関心を持ってもらいたい、という想いを込めて、この名前をつけました。
町内産の野菜は長ネギ、ほうれん草、生しいたけの使用を予定しています。小麦粉は町内の小動で育った小麦を粉にしてもらったものを使って、団子にします。
寒川産以外にも、津久井在来大豆を使用した味噌や神奈川県内産の野菜(白菜・にんじんなど)も使って、身近に育つ食べ物で、食欲の秋を楽しんでもらいたいと思います。
「高座」のこころ。鍋の作り方
【材料】(4人分)グラム
豚小間 40 小麦粉 32 水 大匙1
にんじん 40 生しいたけ 20 白菜 80
長ねぎ 40 ほうれん草 40 板こんにゃく40
油揚げ 1枚 味噌 36 煮干し 4
【作り方】
- 煮干しでだしをとる。
- にんじんはいちょう切り、しいたけ4分の1、白菜は、ざく切り、長ねぎは斜め切り、 ほうれん草は下茹でしてから3センチメートルに切る。
- 小麦粉を水でこねてしばらく置いておく。(水量は、耳たぶくらいのかたさに調節してください)団子にしてゆでておく。
- 鍋にだし汁をいれ、材料を入れて煮立たせ、あくをとる。
- 味噌で味を整える。 団子とゆでたほうれん草を加えて、出来上がり。
【旬とは】
今は一年中食べたいものを手に入れることができるようになりました。しかし食べ物にはそれぞれの地域でよく育ち、たくさんとれる季節があります。食べ物が一番おいしくて、栄養もたっぷりで、たくさんとれる時期のことを旬といいます。
寒川町で育つ、秋が旬の食べ物を探してみましょう。
【旬の食べ物 1】 ≪さつまいも≫
寒川町の畑でも収穫されるさつまいもは、ビタミンB1・Cなどの栄養素が含まれています。不足しがちな食物繊維もたくさんとれます。焼き芋・蒸し芋・煮物・天ぷら・きんとん・デザートなど、幅広い料理に使えます。切ったらすぐに水につけてあく抜きをします。あくの成分は皮に多いので、きんとんやデザートを作るときには厚めにむきましょう。
寒さに弱いので、冷蔵庫で長く保存することはできません。新聞紙でつつみ、風通しがよく日の当たらない場所で保存するとよいでしょう。
給食では、10月に「大学芋」や、「芋栗ごはん」にさつまいもが登場します。
【旬の食べ物 2】 ≪栗≫
木の実は脂質が多いのが特徴ですが、栗は糖質を主成分としています。日本では、栗が縄文時代から食べられていることがわかっています。ビタミンB₁やビタミンCがたくさん含まれており、渋皮煮にするとポリフェノールも摂取することができます。
栗は、皮にツヤがあるもの。ずっしりと重いもの。ふっくらとしていて丸みのあるもの。穴があいていないものを選びましょう。生の栗は空気穴をあけたビニール袋に入れて保存しましょう。
給食では、10月に「栗ご飯」が登場します。
【学校給食とは】
「学校給食法」に基づき教育活動の一環として実施されるものです。成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、望ましい食習慣と食に関する実践力を身に着けるための重要な教材としての役割も担っています。
【学校給食の目標】
- 適切な栄養の摂取による健康の保持増進。
- 食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営む判断力や、望ましい食習慣を養う。
- 明るい社会性と協同の精神を養う。
- 自然の恩恵への理解を深め、生命、自然を尊重する精神や環境の保全に寄与する態度を養う。
- 食生活が多くの人々の勤労に支えられていることを理解し、感謝する。
- 伝統的な食文化を理解する。
- 食料の生産、流通および消費について、正しく理解する。
この記事に関するお問い合わせ先
寒川学校給食センター
住所:253-0106
神奈川県高座郡寒川町宮山4018番地
電話:0467-75-6706
ファクス:0467-75-6707
メールフォームによるお問い合わせ

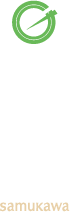


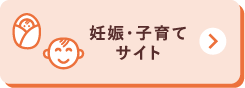
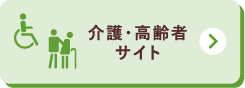





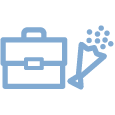





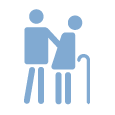

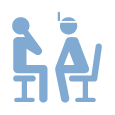



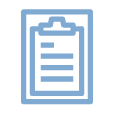

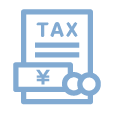

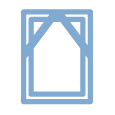

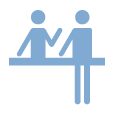



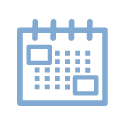





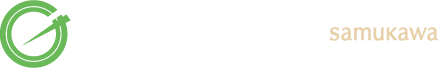
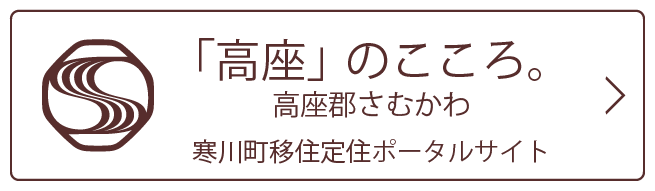
更新日:2024年10月30日