ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るために医療費の保険診療分の自己負担分を助成する制度です。
注釈:入院時食事療養費標準負担額は助成されません。
健康保険証の新規発行終了に伴う保険資格情報の確認について
令和6年12月2日より健康保険証の新規発行は終了となり、保険資格情報がマイナンバーカードに一本化される予定となっています。
詳細については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
ただし、当町におけるマイナンバーを用いた情報連携による保険資格情報の確認は、令和7年6月以降の開始となります。
そのため、令和6年12月2日以降も福祉医療証の各種お手続き(新規申請・保険変更等)の際は、下記書類等のご提出をお願いします。
|
必要書類等(いずれか1点) |
詳細 |
|
1.現在所有している保険証 (有効期限内のもの) |
お手持ちの保険証は、記載事項に変更がない場合、記載されている有効期限まで(有効期限が記載されていないものは令和7年12月1日まで)利用可能です。 |
|
2.資格情報のお知らせ |
マイナ保険証への移行がお済みの方へ発行されます。 発行等に関することは、加入されている保険証の発行元へお問い合わせください。 |
|
3.資格確認書 |
マイナ保険証への移行がお済みでない方へ発行されます。 発行等に関することは、加入されている保険証の発行元へお問い合わせください。 |
|
4.マイナポータル画面 |
マイナ保険証への移行がお済みの方で資格情報のお知らせをお持ちでない方は、ご自身のスマートフォン等でマイナポータルにログインし、保険資格情報が確認できる画面をご提示ください。 |
注釈:ご案内の内容については、随時更新します。
注釈:1~4について、氏名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認のうえ、ご提出ください。
対象者
町内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護するひとり親家庭等(父子家庭、母子家庭、養育者家庭)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が規則で定める障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母がともに不明である児童(孤児など)
助成期間
児童が満18歳になった日以後の最初の3月31日まで(規則で定める程度の障害がある場合、または高等学校等に在学している場合は20歳未満まで)
所得制限
前々年分の所得及び税法上の扶養人数で決まります。それぞれ限度額を超える場合は、福祉医療証の対象となりません。
|
扶養人数 |
ひとり親・養育者 |
配偶者・扶養義務者 |
| 0人 | 208万円 未満 | 236万円 未満 |
| 1人 | 246万円 未満 | 274万円 未満 |
| 2人 | 284万円 未満 | 312万円 未満 |
| 3人 | 322万円 未満 | 350万円 未満 |
| 4人 | 360万円 未満 | 388万円 未満 |
注釈:所得額から社会保険料等控除額(一律8万円)、その他医療費控除等を差し引いた金額です。
助成を受ける方法
神奈川県内の医療機関を受診するときに、健康保険証と一緒に町が交付する福祉医療証を窓口に提示してください。医療費の保険診療分の自己負担額を支払わずに受診できます。
神奈川県外の医療機関や、県内でも福祉医療証が使用できなかったときは、医療費の保険診療分の自己負担額を支払い、受診した月の翌月から1年以内に子育て支援課へ申請し、償還払い(口座振込での払い戻し)の手続きをしてください。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 福祉医療証
- 保険資格情報が確認できる書類等(詳細は、ページ上部「健康保険証の新規発行終了に伴う保険資格情報の確認について」をご覧ください。)
- 印鑑
- 領収書(患者氏名・保険診療の総合点・診療期間・領収金額・医療機関名の記載があるもの)
- 預金通帳
- 高額療養費及び療養費払いとなる医療費については、保険者からの支払いがわかるもの(支給決定通知等)
福祉医療証の申請
助成を受けるためには福祉医療証の交付申請が必要です。
必要書類等は世帯によって異なりますので、申請を希望する方は子育て支援課へご相談ください。
その他の手続き
保険資格情報や住所等が変わったとき、福祉医療証を紛失したときなどは届出が必要です。
~お願い~
保育園や学校管理下の事由による負傷・疾病等の場合は、学校等で加入している保険が対象となりますので、福祉医療証は使用せずに受診してください。詳細については、学校等にお問い合わせください。
交通事故など第三者の行為によるケガなどの治療費は、原則として、その加害者が負担すべきものですので、福祉医療証は使用しないでください。
注意事項
次のような場合は、本制度を受けることができません。
- ひとり親家庭の父または母が、異性と同居している(事実婚状態にある)とき。
- 対象となる児童が児童福祉施設に入所していたり、里親に預けられているとき。
ひとり親家庭・総合支援情報サイト、SNS相談
ひとり親家庭・総合支援情報サイト「カナ・カモミール」(神奈川県)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ

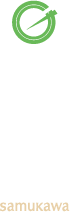


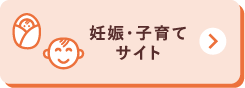
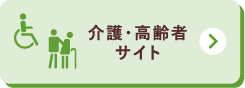





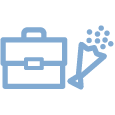





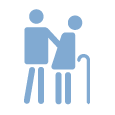

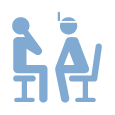



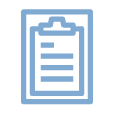

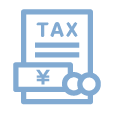

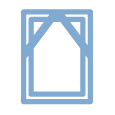

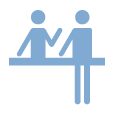



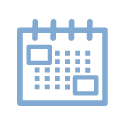





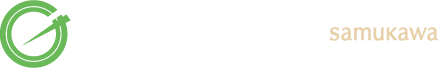
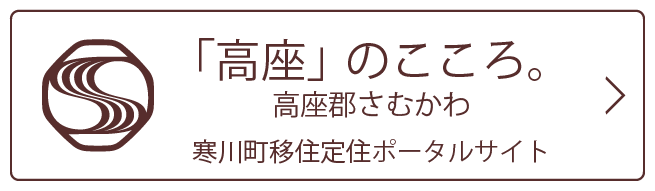
更新日:2024年12月16日