小児医療費助成制度
寒川町小児医療費助成制度について
この制度は、お子さまが病院等で受診したときに支払う医療費のうち、保険診療分の自己負担額を助成するものです。これにより、医療機関にかかる際にマイナ保険証等と小児医療証(小児医療費助成を受ける資格があることを証明する書類)を窓口に提示すると、保険診療分の医療費が無料になります。
対象となる子ども
【令和5年10月から】
0歳から高校3年生相当(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子ども
【注意事項】
ただし、次に該当する人は除きます。
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設に入所している人
- 里親に託されている人
- 重度障害者等医療費助成やひとり親家庭等医療費助成を受けている人
この事業は、保護者に養育されている児童が対象となるため、児童が就労等により保護者に扶養されていないなどの場合は、対象外となる可能性があります。
【お知らせ】
令和5年10月診療分から、対象年齢を中学校3年生までから高校3年生相当(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までに拡充しました。助成を受けるためには、申請が必要です。(下記の「小児医療証の申請に必要なもの」をご参照ください。)
令和5年9月11日までに申請書が受理された方には、令和5年9月26日に医療証を発送しました。令和5年9月12日以降に受理された方については、順次発送となります。申請後、医療証が届くまでの間に病院等を受診した場合は、子育て支援課に払い戻しの申請をしてください。(下記の「払い戻しの申請に必要なもの」をご参照ください。)
保護者の所得制限
なし
【注意事項】
- 保護者の所得制限はありませんが、補助金の申請のため所得を判定しています。未申告等により所得の確認ができない場合は補助金の対象外となるため、所得の申告等にご協力をお願いします。
助成される医療費
国民健康保険または各医療保険を使って受ける医療費のうち、保険診療分の自己負担額
【注意事項】
- 入院時食事療養費標準負担額は助成されません。
- 保険が適用されないものは助成されません(健診、予防接種、初診時特定療養費、薬の容器代、文書料、差額ベッド代など)。
- 健康保険組合などから支給される付加給付や他の公費負担医療などの適用がある場合は、その金額を控除した額が助成されます。
- 小児医療証は神奈川県内の医療機関のみで使えます。神奈川県外の医療機関にかかった場合は、子育て支援課へ払い戻しの申請をしてください。
小児医療証の申請に必要なもの
次の書類をご用意のうえ、子育て支援課へ申請してください。対象となるお子さまには小児医療証を交付します。
- 小児医療費助成事業医療証交付申請書
- 子どもの健康保険資格情報が分かるもの(注意1)
- 保護者と子どもの個人番号が分かるもの(個人番号カード・通知カード等)
【注意事項】
- 小児医療証の有効期間は、お子さまのお誕生月の月末までとなります。
- 有効期間が切れる前に新しい小児医療証をお送りします。(医療証は誕生月の20日頃に発送しています。)
- 有効期間が切れた小児医療証は裁断・破棄していただくか、子育て支援課窓口に返却してください。
- 神奈川県外の国民健康保険組合(全国建設工事業国民健康保険組合および全国土木建築国民健康保険組合を除く)に加入している場合は、小児医療証の交付を受けることはできません。医療機関にかかった場合は、子育て支援課へ払い戻しの申請をしてください。
(注意1)令和6年12月2日より現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードに一本化される予定です。
ただし、当町におけるマイナンバーを用いた情報連携による保険資格情報の確認は、令和7年6月以降開始となります。つきましては、お手数ですが医療費助成の各種お手続きの際は、令和6年12月2日以降も引き続き下記書類のうちいずれか1点をご提示ください。(児童名、保険者番号、保険者名、記号・番号、被保険者名、資格取得日が記載されていることをご確認ください)
(1)現在所有している保険証
記載事項に変更がない場合、令和7年12月1日までは現在の保険証が使用可能です。
有効期限の記載があるものはその期限まで使用可能です。
(2)資格情報のお知らせ 医療保険の保険者から発行されたもの。
(3)資格確認書 医療保険の保険者から発行されたもの。
(4)マイナポータルの資格情報画面、もしくはそのスクリーンショット等
医療機関にかかるとき
医療機関にかかる際は下表を参照してください。
原則、医療機関窓口で医療費の支払いはありませんが、これはみなさんに納めていただいた税金から医療機関へ支払っているためです。この制度を維持していくためにも、適正受診・ジェネリック医薬品への切り替え等にご協力をお願いします。
|
神奈川県内の医療機関にかかる場合 |
マイナ保険証等と小児医療証を医療機関の窓口に提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。 |
|---|---|
|
神奈川 |
マイナ保険証等のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。 |
|
小児医療証を忘れた場合 |
マイナ保険証等のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。 |
|
保険証を忘れた場合 |
医療費を全額自己負担し、健康保険組合へ保険負担分の払い戻しの申請をしてください。 |
|
神奈川県外の国民健康保険組合に加入している場合 |
マイナ保険証等のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。 保険診療分の自己負担額については子育て支援課へ申請し、払い戻しを受けてください。 |
|
補装具等を作成した場合 |
医療費を全額自己負担し、健康保険組合へ保険負担分の払い戻しの申請をしてください。 |
|
交通事故等によりけがをした場合 |
原則として医療費は加害者が負担することになるため、マイナ保険証等や小児医療証は使用しないでください。 |
|
学校でけがをした場合(登下校中含む) |
マイナ保険証等のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。 |
払い戻しの申請に必要なもの
次の書類をご用意のうえ、診療日の1年後の同月末まで(注意2)に子育て支援課へ申請してください。
- 小児医療費助成申請書
- 小児医療証
- 子どもの健康保険資格情報がわかるもの(注意1)
- 領収書(患者氏名、保険診療の総合点、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
- 申請する人の預金通帳(お子様名義の口座は指定できかねます。保護者様名義の口座が分かるものをご用意ください)
- 申請者と子どもの個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 健康保険組合の保険者からの支払いがわかるもの(支給決定通知書等)
- 医師の指示書等
【注意事項】
- 7は保険証を忘れた場合および補装具等を作成した場合に必要です。
- 8は補装具等を作成した場合に必要です。
- 4と7の両方が必要な場合、どちらかは原本が必要です。
(注意2)払い戻しの申請期限(時効)は、医療機関の窓口で保険診療分の自己負担額を支払った日の翌日から起算して5年です。
ただし、加入している健康保険組合への医療費の払い戻しの申請期限(時効)は2年です。補装具を購入した場合や、医療費を10割負担された場合は、申請期限にご注意ください。
その他の手続き
次の書類をご用意のうえ、子育て支援課へ申請してください。
|
子どもの健康保険資格情報が変わった場合 |
|
|---|---|
|
町内で転居した場合 |
|
|
町外へ転出した場合 |
|
|
重度障害者等医療費助成に変更となった場合 |
|
|
ひとり親家庭等医療費助成に変更となった場合 |
|
|
生活保護を開始した場合 |
|
|
小児医療証を紛失・汚損した場合 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ

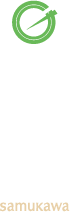


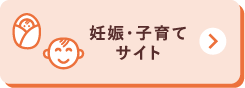
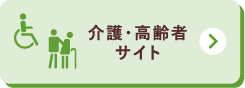





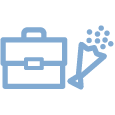





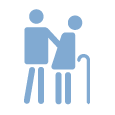

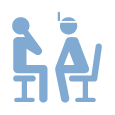



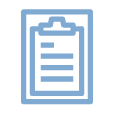

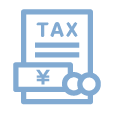

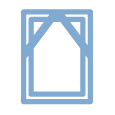

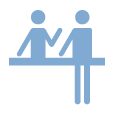



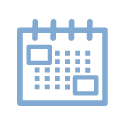





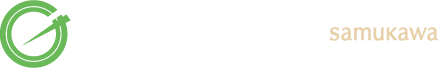
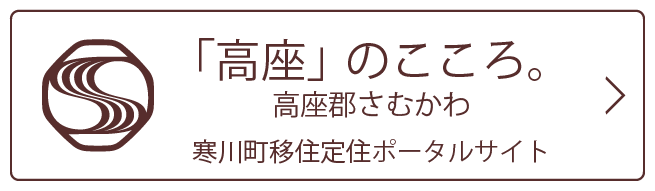
更新日:2024年12月02日