特集 おいしいみんなの学校給食―令和5年9月 給食センター オープン―
問い合わせ先
教育施設給食課 電話74-1111 内線542 施設・給食担当 ファクス75-9907
町の学校給食の「いままで」と「これから」
現在、町立小学校では、校内にある給食室で調理を行う「自校式」で、完全給食の提供を行なっています。しかし、学校施設の老朽化とともに、各学校の給食室や厨房機器等に多くの修繕が必要となっているという課題があります。
また、町立中学校では、主食やおかずは生徒がお弁当を持参し、学校では牛乳のみを提供する「ミルク給食」を実施しています。近年では、生活スタイルの変化からお弁当を用意することが難しい家庭もあり、課題となっています。
一方、全国の公立中学校においては、各都道府県の平均で約9割が、主食やおかず等からなる完全給食を実施しています。しかし、県の公立中学校の完全給食実施率は約4割です(『平成30年度学校給食実施状況等調査』より)。
こういった現状を踏まえ、町では検討を重ねた上で「(仮称)寒川町学校給食センター」を建設し、町立小・中学校全校で完全給食を実施することとしました。
給食センターを建設・運営する上での根幹となる「寒川町学校給食センター整備基本構想・計画」では、町で学校に通う子どもたちの未来のため、日々成長する過程で大事な給食を「将来にわたって、安全・安心でおいしく」提供することを目標としています。この目標を達成すべく、検討をさらに重ねながら、給食センターの建設を進めていきます。
給食提供のこころ
町では、「寒川町学校給食センター整備基本構想・計画」の中で、町の学校給食が目指す基本方針である「給食提供のこころ」を示しています。
この「給食提供のこころ」は、基本方針の根幹である「未来へむかって みんなが笑顔で 楽しく食べる」を達成するために、8つのテーマごとの方針が支えているつくりとなっています。
未来へむかって みんなが笑顔で 楽しく食べる
- 人とシステムによる安全性の確保
- 五感で楽しむ給食の提供
- 食育のさらなる推進
- 食物アレルギーへの十分な対応
- 地産地消の推進
- 調理環境の充実
- 環境負荷への配慮
- 未来を見据えた社会ニーズへの対応
こんなことが変わります
中学校で完全給食の提供が開始されます
現在、中学校では牛乳のみを提供するミルク給食が実施されていますが、令和5年度からは、主食やおかずなども含めた完全給食が提供される予定です。
さらに安全・安心な学校給食が提供されます
基本方針である「給食提供のこころ」に基づいた衛生管理や最新式の厨房機器により、これまで以上に安全・安心な学校給食が提供されます。ほかの部屋から独立した、専用の調理室を用意し、食物アレルギーへの対応も行なっていきます。
町の「食育」発信基地として整備されます
給食センターは、学校給食を児童生徒に提供するだけでなく、すべての町民に食べることの楽しさ・大切さを伝える「食育」のための施設として整備されます。給食の調理風景を目の前で見ることができる見学通路や充実した食育スペースを整備し、「食育」発信基地として活躍していきます。
( 仮称)寒川町学校給食センター 完成イメージ図

作り手のかおが見える見学通路
安全・安心でおいしい給食の調理風景を目の前で見学できます。
充実した食育スペース
食育実習室を併設し、一度に120人が使用できます。隣室のキッチンスペースでは、調理実習を行うことができます。
温かい給食を学校へお届け
できたてで温かい給食を、すぐに小・中学校へ運びます。
食の広場
正面玄関前の広場では、さまざまな食育イベントを開催する予定です。
建設予定地
住所 寒川町宮山4018番地ほか
敷地面積 4,500平方メートル程度
各階の設備
1階 食材のフロア
荷受室、洗浄室、事務室 など
2階 調理のフロア
下処理室、調理室、見学通路 など
3階 学びのフロア
食育実習室、キッチンスペース など
町の栄養士トークルーム -子どもの健康な身体(からだ)のために-
各町立小学校に配属されている学校栄養士は、日々子どもたちが食べる給食の献立づくりや栄養管理を行います。また、「食べる」ことの楽しさ・大切さを子どもたちに伝える「食に関する指導」もしています。今回は、5人の学校栄養士の座談会から、給食の「リアル」をお届けします。
座談会参加メンバー
- 鈴木学校栄養主査(寒川小学校)
- 内田栄養士(一之宮小学校)
- 箭内(やない)栄養教諭(旭小学校)
- 渡邊管理栄養士(小谷小学校)
- 木村栄養士(南小学校)
「おいしい」へのこだわり
渡邊 おいしく作ることを第一に考えていますね。おいしくないと、子どもたちも食べてくれないし、私たちが食に関する指導をしても説得力がなくなってしまうと思うんです。
内田 おいしいことは本当に大事ですね。
鈴木 出汁の取り方はみんな気にしていると思います。素材から取っていたり、昆布・カツオ・煮干し、それぞれ献立によって使い分けたりしています。
箭内 調理の仕方にもこだわっています。カレーやシチューを作るときは、玉ねぎを色が変わるまで炒めるとか、煮込んでいる間に野菜が崩れないように…とか。
木村 下味をしっかりと付けることも意識しています。冷凍のお魚は塩こうじなどで臭みを取ってあげると、子どもたちも食べやすいみたいで…子どもたちにとって「おいしい」給食を心掛けていますね。
鈴木 調理員さんもすごく工夫してくれますよね。食材を何センチ角に切ってほしいとか、細かいこともしっかりと対応してくれて。栄養士・調理員さん共に協力しながらこだわって作っていますね。
渡邊 そういった細かな気配りによって、子どもたちが食べてくれるんです。例えば、キャベツの芯を薄く切るようにしたら、残食の量が減ったり。やっぱり「おいしく食べてもらえる」給食にするにはどうしたらいいかを常に考えています。
箭内 おいしく作ることと同様に、「安全・安心に」作ることも大事にしています。こんなところまで!というレベルまで、異物が入っていないか等の確認をします。パンをひとつひとつしっかりと見て異常がないか確認したり、お米を少しずつ注いで異物が入っていないか確認したり… 複数人でできないときは、複数回チェックしています。
渡邊 「おいしくて、安全な給食」というみんなの共通目標があるから、厳しくチェックしていますね。
子どもたちとのつながり
渡邊 やっぱり子どもたちへの声掛けが中心になりますね。クラスを回って、担任の先生と情報交換をしながら、子どもたちの話をゆっくりと聞いてみるとか。苦手な食べ物はある?って聞いてみたりもします。
箭内 「家だと食べないけど、給食だと食べるみたいで」と保護者の方からお話をいただくことも多いですよね。
鈴木 クラスのみんなと一緒に楽しい雰囲気の中で食べているから、苦手なものも食べられるってこともありますね。最近は新型コロナウイルス感染症の関係でそれが難しいけれど…。
木村 嫌いな食べ物がある子どもに、「全部食べたら『おめでとう』を言いたいから教えてね」という声掛けをしたら、こっそり「全部食べたよ」と伝えに来てくれて、「おめでとう!」と2人で喜び合ったことがあります。
箭内 給食が好きで、私と会うと「お腹がすいた」と話す子どももいます。体調を崩さないように、しっかりと朝ごはんも大切にして食べてほしいものですね。
寒川の「食育」キャラクター
鈴木 体を作る「赤兵衛」・エネルギー源の「黄々丸」・体の調子を整える「お緑」。3つの食べ物の働きを表現した忍者のキャラクターを使って、食べ物の栄養・摂取バランスについて考えてもらえるようにしています。
内田 親しみやすさを意識して作りました。子どもたちがイラストを描いてくれることもあります。卒業生が覚えていてくれたときはうれしかったですね。
給食の「ミライ」
鈴木 3年後に給食センターの運営が始まりますが、学校栄養士としては、小学校6年間の成長を見てきた子どもたちに、中学生になっても「給食」を通して関われることがうれしいです。中学校でも給食をおいしく食べてもらえたらなと思います。
箭内 現在、中学校はお弁当持参ですが、栄養バランスが整ったお弁当を毎日用意するのは、保護者の方もなかなか大変ですよね。給食を提供することで、そういった負担を減らせるとよいなと思います。
渡邊 給食センターならではの食育を研究していく必要があると思います。やらなくてはいけないことは見えているので、それをどのように実現していくのか、運用が始まるまでの3年間で考えていくことが課題ですね。
各町立小学校 人気メニュー紹介
寒川小学校
ジャンボぎょうざ
特別な大きい皮を使用した、ボリュームもインパクトも大きいぎょうざ。
一之宮小学校
フルーツミックス
校内で実施した人気投票で上位に。揚げパンやカレーライスも人気。
旭小学校
揚げパン
きなこ、シナモン、抹茶など味はさまざま。試食会でリクエストされることも。
小谷小学校
ごぼうの唐揚げ
からりと揚げて、塩を振ったもの。
南小学校
キムタクごはん
長野県の給食メニューをオリジナルにアレンジ。
栄養士からひとこと
鈴木学校栄養主査(寒川小学校)
「いろいろな食品を食べるのがいいんですよね。栄養価だけじゃなくて、食材の持っている力がそれぞれなので。」
内田栄養士(一之宮小学校)
「すべての献立が出馬する給食総選挙を開催したことがあります。みんな盛り上がって投票してくれました。」
箭内栄養教諭(旭小学校)
「子どもたちの健康のためには、小さいころからの食育が大事ですね。」
渡邊管理栄養士(小谷小学校)
「ごぼうの唐揚げは、たくさんのごぼうを給食室総出で切るので、みんな手が真っ黒になります。子どもたちが黒い手を見に来たことも。」
木村栄養士(南小学校)
「子どもに「“キムラ先生が炊くごはん”だからキムタクごはんでしょ?」と言われました(笑) キムチとたくあんで、「キムタクごはん」です。」
給食センター整備年表
昭和33年4月 町で学校給食が初めて提供される
- 寒川小学校で、完全給食の提供が始まる
- 他町立小・中学校でも、順次、給食が開始
平成29年11月 給食センターを整備することとする
外部の有識者を含めた会議の意見を踏まえ、内部の会議を開催し、町の学校給食センターに対する考え方や整備計画を検討
令和元年9月 「寒川町学校給食センター整備基本構想・計画」策定
- 学校の先生や給食業務に携わる栄養士・調理員と町職員で構成する会議を開催し、給食センターの図面や、その運用方法について検討
- 基本設計完了(令和2年8月末)
令和3年8月から令和5年3月 給食センター建設工事の開始、完成
給食センターによる給食提供開始の点検・準備
令和5年9月(予定) 町立小・中学校へ給食センターによる完全給食の提供が始まる
この記事に関するお問い合わせ先
広報戦略課広報プロモーション担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:241、242、243)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ

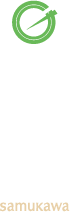


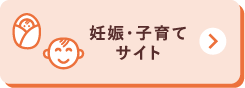
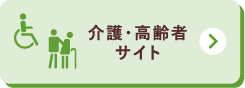





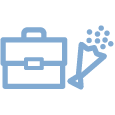





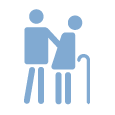

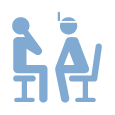



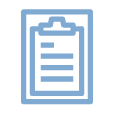

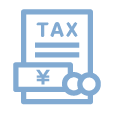

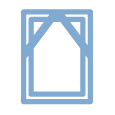

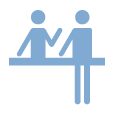



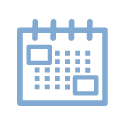





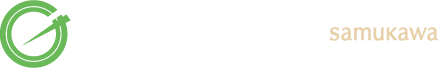
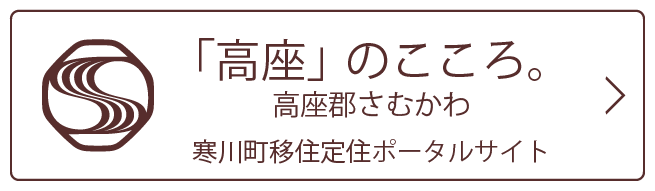
更新日:2020年09月27日