令和7年度 施政方針
本日、令和7年寒川町議会第2回定例会3月会議開会にあたり、令和7年度予算案をはじめ関係諸議案を提出し、審議をお願いするわけでございますが、予算案等の提案に先立ちまして、私の町政に対する基本的な考え方や施策の概要について申し述べ、議員各位ならびに町民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
(はじめに)
町議会におかれましては、より開かれた議会をめざし、議会改革を推進する中、先月行われました町議会議員選挙により、新たな顔ぶれによる議会が構成され、スタートしたことに、敬意を表するとともに心からお喜び申し上げます。
これからも町民の代表である議員の皆様と、ともに力を合わせながら、町民皆様の安全・安心と、こころ豊かな暮らしの実現をめざしてまいります。
さて、本年2月の内閣府月例経済報告では、「景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。」とされ、「先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、通商政策などアメリカの政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」とされております。
こうした社会経済情勢の中、町の財政状況については、国・県ともに、今後、景気は緩やかに回復していくことが想定され、町においても、引き続き堅調な町税収入が期待できるものの、景気等の影響による下振れリスクにも十分留意し、寒川町総合計画2040に掲げるまちの将来像「つながる力で 新化するまち」の実現のため、将来を見据えた各事務事業を効果的・効率的に進めるとともに、持続可能なまちづくりに取り組んでまいります。
(町政に対する基本的な考え方)
それでは、町政に対する基本的な考え方について申し上げます。
日本を取り巻く社会経済環境は複雑な要因が絡み合い、多くの課題に直面しております。
特に社会経済は、長期的な低成長の傾向から脱却しようとしております。グローバルな経済回復や政府の経済政策の効果により、一部の指標では改善が見られますが、少子高齢化に伴う労働力不足、賃金の伸び悩み、地域間格差など、依然として構造的な課題が山積しております。
また、日本は超高齢社会に突入しており、65歳以上の人口の割合が高まっております。これにより、年金や医療、介護といった社会保障制度への負担が増加している一方で、高齢者の働く意欲を引き出す政策も重要視されております。
さらには、昨今の気候変動への対応として再生可能エネルギーの導入や省エネルギーに向けた取り組みが重要視され、「パリ協定」に基づく温室効果ガス排出量削減目標の達成も課題となっております。
国際関係においては、地政学的な緊張や経済的な競争が影響を与えております。特に、アメリカとの経済関係や中国との関係は、日本の経済政策に大きな影響を及ぼしています。
これら日本を取り巻く社会経済環境は、本町にも少なからず影響を与えております。
こうした状況の中、本年は寒川町総合計画2040第2次実施計画及び第3期寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略のスタートの年であります。
寒川町総合計画2040の基本構想においては、「町民と町が協働するまちづくり」をまちづくりの理念とし、まちの将来像を「つながる力で 新化するまち」と位置付けております。その実現のため、本年度から令和10年度までの4年間を計画期間とする第2次実施計画では、各施策・事務事業の具体的な取り組みを定め、選択と集中の考えのもとスピード感を持った町政運営に努めてまいります。
また、まち・ひと・しごと創生総合戦略については、少子高齢化・人口減少への対応が依然として課題であります。町総合計画2040第2次実施計画に包含する第3期では、地域ビジョンや町ブランドを設定し、町の魅力や個性を生かした地域課題の解決をめざすため、持続可能な地域経済の実現に向けた中小企業支援をはじめ、町民による発信力の強化や関係人口の獲得、結婚を希望する方への支援、子育て世帯のゆとりの創出や魅力的な教育環境の充実などのほか、デジタル技術の活用といった新たな視点も取り入れながら進めてまいります。
これらの取り組みを進めるにあたりまして、多様化・複雑化する町民ニーズを的確に把握し、その本質を見極めながら適時適切な政策の構築と、効果的かつ効率的な課題解決を可能とする行政組織に改めます。
また、公共施設の老朽化・更新問題として、町立小・中学校の適正規模・適正配置等の検討に基づく配置場所について一定の結論が出たところではありますが、将来的に学校が建て替えられていくまでの現行の機能維持として、児童生徒の生活の場でもある学校の安全を第一と考え、本年度は小学校では小学校5校の体育館屋根改修工事及びそれに伴う工事監理委託と一之宮小学校北棟屋上防水改修工事を予定しており、中学校では中学校3校の体育館屋根修繕設計委託と旭が丘中学校技術棟屋根修繕設計委託を予定しております。
さらに、町立小・中学校の適正規模・適正配置等については、将来の寒川の子どもたちにとって望ましい教育環境の確保と地域コミュニティの拠点となる施設整備の実現に向け、学校を中心とした公共施設の複合化や多機能化の具体的な検討を進めてまいります。
そのため、庁内横断的な検討体制を構築するとともに、公共施設再編計画に基づき、PPP/PFI手法といった民間資金や民間事業者のノウハウやアイデアを積極的に活用し、財政負担の軽減・平準化を図りつつ、公共施設の最適配置をめざしてまいります。
広域行政につきましては、これまでも地域的な結びつきの強さを生かした取り組みを進めてきたところでありますが、先行き不透明な社会経済環境の中では、市町が連携することで効果的な事業展開が図られるとともに、財政面からも各種補助金の獲得が可能となるなど、広域行政の優位性は年々高まりを見せていることから、引き続き市町共通の課題解決に向けた取り組みを進めてまいります。
(主な事業)
町のブランドスローガン『「高座」のこころ。』に表わされる「穏やかさ、優しさ、あたたかさ」を念頭に置き、町総合計画2040のまちの将来像「つながる力で 新化するまち」の実現に向け、6つの基本目標と12の政策により、計画実効性と財政の健全性を担保しながら、まちづくりを推進してまいります。
それでは、新規事業を中心に、本年度実施する事業につきましてご説明申し上げます。
はじめに、1つ目の基本目標といたしまして「まちづくりの原動力となるひとづくり」です。
<子育て支援の充実><子どもの育ち・発達の支援>
町では、本年4月から子ども・子育て支援法に位置付けられる産後ケア事業ならびに妊婦のための支援給付及び利用者支援事業を着実に実施するとともに、ヤングケアラーに対する認知度を高め、理解を深めるための研修を関係機関の職員を対象に開催するなど、妊娠・出産から子育てまで、子育て家庭に寄り添った切れ目ない支援の充実に一層努めてまいります。
また、乳幼児の保育需要が増加している状況を踏まえ、本年4月に認定こども園に移行する施設に対し、給付費や補助金等の交付により運営に対する支援を行うとともに、既存保育施設の老朽化した設備や備品等の修繕に対する補助を行うことで安全に児童をお預かりできる施設としてまいります。
さらに、保育士確保のための保育士宿舎借り上げ支援事業や、保育士資格を有しない者が保育に係る周辺業務を行うことで保育士の負担軽減に繋がる補助、加配保育士に対する補助の増額等を行ってまいります。こうした負担軽減に繋がる補助等を行うことで就業継続、離職防止や新規保育士の確保を図り、施設整備と保育の質の両面において保育環境を整えてまいります。
児童クラブにつきましては、共働きの子育て世帯の増加等により入所希望者が増えており、待機児童が生じております。
こうした状況の中、夏休みの長期期間中の保育ニーズに的確に対応するため、本年度は共働き世帯の小学生を対象として新たにサマースクールの試験的実施を行います。これにより年間を通じた保育ニーズを的確に把握することで児童クラブの待機児童解消に努めてまいります。
これらの取り組みを通じて、湘南地域で最も子育てしやすいまちをめざしてまいります。
<学校教育の推進>
次に、学校教育の推進につきましては、グローバル社会において、将来活躍する子どもたちを育むために、特に外国語教育とICT教育といった、大きく2つのアプローチからこれまで特色ある教育振興を進めてまいりました。
英語教員免許を所有する外国人指導者(FLT)を県内で初めて全校常駐配置し、専門性の高い英語授業を展開するとともに、GIGAスクール構想の推進により1人1台タブレット端末の効果的な活用を進めてきたところであります。
そうした中で、令和5年度においては、英語検定等を受験する生徒が大幅に減少しました。その一因として、近年の英語人材不足・物価高騰の影響を受け、受験料が高騰していることなどが挙げられます。
英語検定などの外部検定は、子どもたちが英語を学ぶ上での自らの力を測ることができる機会、そしてさらなる学びへの動機づけやきっかけとなり、英語力向上につながるものであります。
そこで、高校・大学入試においては、英語検定などの成績を合否判定に利用する学校が多いことから、新たに町内の中学生が、英語検定3級を受験する際の検定料を助成することで、入試における優位性の確保を通して、子どもたちの学習意欲、さらには英語力の向上を図ることをめざしてまいります。
また、GIGAスクール構想による1人1台タブレット端末の導入につきましては、令和8年度に5年目を迎え、耐用年数が迫る中、全国的に端末の入れ替えの時期となります。
このような状況を踏まえ、小・中学校における児童生徒・教職員のタブレット端末の更新につきましては、本年度及び令和8年度の2年間で、国の補助金を活用しつつ、県を中心とした共同調達を通じてスケール・メリットを生かしながら計画的に端末更新を進めてまいります。
今日、学校教育は、障がいのある子どもの自立と社会参加をめざした取り組みを含め、「共生社会」の形成に向けて重要な役割を果たすことが求められております。本町では、他市町村に先んじて町内の全小・中学校に特別支援学級を設置するとともに、子どもたちの発達に応じた教育が展開できるよう、一之宮小学校と小谷小学校に通級指導教室、いわゆる「ことばの教室」を設置し、「誰一人取り残さない支援教育」の実現に向けて力を入れてまいりました。
しかしながら、通級指導教室の設置校以外の児童は、安全上、保護者による送迎が必要であるため、通級指導教室における課題となっておりました。
その課題を解決するため、県内及び全国に先駆けて、本年度から町内全小学校における通級指導教室の設置・運用開始を行います。
また、中学校に通級指導教室が未設置であることから、小学校卒業後に中学校で発達段階や特性に応じた指導を受けることができない状況のため、系統的・継続的な通級指導が課題となっております。
そのため、町内全中学校における通級指導教室の設置をめざして、本年度に施設面の整備を図り、令和8年度の運用開始を進めてまいります。
これにより、町内すべての児童生徒が、誰一人取り残されずに、一人ひとりの特性に応じた教育を受けることができる教育環境を整備してまいります。
次に、教職員の働き方改革の推進につきましては、国の教員勤務実態調査の結果、長時間勤務について看過できない深刻な状況となっており、本町においても喫緊の課題となっております。こうした教職員の多忙化の背景には、社会環境の変化に伴い、学校を取り巻く環境が複雑化・多様化しており、学校に求められる役割が拡大していることが挙げられます。
その課題解消に向けて、これまで教員の事務作業を支援するスクールサポートスタッフの配置をはじめ、児童生徒や保護者からの相談等に専門的な立場から対応を行うスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、心理士、巡回指導員を県の措置と併せて配置するとともに、「ふれあい教育支援員」や「特別支援学級補助員」など、外部人材も積極的に配置してまいりました。
さらには、学校留守番電話の設置や学校閉庁日、部活動休養日を設定するほか、「勤怠管理システム」や「校務支援システム」を導入するとともに、給食費の公会計化や、朝の欠席連絡受付の自動化・データ化につながる「欠席連絡ツール」を導入するなど、教職員の事務の効率化・軽減を進めてまいりました。
こうした中、本年度は、中学校の部活動指導について、「部活動指導協力者」を配置するなど、地域人材に段階的に役割を移行し、教職員を含めた担い手による持続可能な部活動運営と、その先の「部活動地域移行」に向けた取り組みを進めてまいります。
また、学校図書館の運営とともに、国語の授業を補佐する「読書指導員」を各小・中学校に配置しておりますが、活字離れによる「読解力」低下への対応が求められる中、その勤務時間・日数を増加させ、教職員とともに読書指導の機会の充実を図ってまいります。
さらに、近年の小学校における教育相談のニーズの高まりに対して、問題行動等の初期対応・支援、保護者等の困り感の解消のため、町心理士の勤務日数を増加させることで、小学校における相談体制の充実を図ってまいります。
加えて、「学級担任制」を実施している小学校において、町独自に補充教員を配置し、学校全体の教育課程を担う教務担当者や、児童の困り感や問題行動等に対してケース会議等を開催し、適切な対応につなげる教育相談コーディネーターの受け持つ授業を分担して軽減することで、組織的に業務を遂行する時間を確保し、円滑な学校運営を図ってまいります。
このように、他自治体に先駆けて、持続可能な勤務環境を整備することにより、教職員が子どもたちと向き合う時間を増やすとともに、学力だけでなく、自ら考え判断し、他者と協働しながら課題解決できる力の向上をめざす授業改善や教材研究に力を注ぐことができる環境づくりを進めてまいります。
次に、学校給食につきましては、社会的な物価高騰が長引く中、家計への負担軽減を図るため、引き続き物価高騰分の公費負担を実施してまいります。
また、給食センターの稼働から1年半余が経過し、生ごみ等の給食残滓排出量がおおむね把握できたことから、学校給食の共同調理場としては県内初の取り組みとなる消滅型の生ごみ処理機を新たに導入し、生ごみ等の運搬及び焼却処理による二酸化炭素の排出を大幅に削減することで、環境へ配慮した施設としての取り組みを進めてまいります。
<スポーツ・レクリエーション活動の推進>
次に、スポーツ・レクリエーション活動の推進につきましては、スポーツ施設の老朽化による施設整備と、若い世代のスポーツ離れが課題となっております。
スポーツ施設の老朽化につきましては、公共施設再編計画及び財政計画と調整を図りながら、利用者ニーズを捉え、優先順位を定め、段階的な改修を行っておりますが、本年度は弓道を楽しむ方が増加する中で、総合体育館建設以来更新していない弓道場内人工芝の張替を行ってまいります。
今後も、引き続き、町民ニーズと社会状況に合った町のスポーツ施策を推進していくために、より有益で高質なスポーツ環境を提供し、町民のだれもが、いつでも、いつまでもスポーツに親しみ、健康で笑顔あふれる地域社会の実現に向け、施設整備を計画的に推進してまいります。
また、若い世代のスポーツ離れについては、全国的にも見られ、本町の中学生においても、スポーツ関連の部活動に所属している生徒の割合が減少している状況にあります。
要因としては、少子高齢化、人口減少、教職員の多忙化等が考えられますが、専門的な指導者の不足が主な原因と考えられます。
そこで、本年度より、公認スポーツ指導者の資格取得者に対する助成制度を創設し、町のスポーツを「ささえる」活動に参画される指導者の確保や育成を行い、スポーツに親しむ若い世代を増やすことで、スポーツ推進施策の更なる強化を図ってまいります。
また、本町においては、2019年にアークリーグ世界大会を開催した後、ストリートスポーツの聖地化をめざし、令和2年度にストリートスポーツパークの建設費を計上したところでありますが、感染症拡大の影響に伴い、感染症拡大防止対策と地域経済の維持を優先し、建設延期の判断をしたところであります。
現在、東京オリンピック、パラリンピックを通じて、ストリートスポーツは、一つの若者文化として依然として人気を博しており、日本全国各地でストリートスポーツパークの建設が進み、地域の魅力向上に大きく貢献している状況であります。
こうしたことを踏まえ、ストリートスポーツのトップアスリートが在住している本町においても、国県等関係機関とも調整を図りながら、パーク建設に向けた取り組みを進めることで、関係人口の確保、移住定住の促進を目的に町の認知度向上を図るとともに、オンリーワンとなる地方創生の実現により「若者からも選ばれるまち」をめざしてまいります。
<生涯学習の推進>
次に、生涯学習の推進につきましては、地域社会のつながりや支えあいが希薄化し、学校が抱える課題も複雑化する中で、今後は地域と学校が連携・協働し、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく活動が重要です。
その推進体制となる「地域学校協働本部」の将来的な設置に向け、引き続き学校運営協議会等との意見交換等を進めてまいります。
また、子どもたちが幼少期から本に親しむことで、読書を通じて、想像力を育み、人生を豊かにする読書習慣を身につけられるよう、子どもの読書活動を充実してまいります。
文化財保護においては、町指定重要文化財である倉見神社本殿の修復に対し、補助金を交付し、町に現存する貴重な文化財の保護、保全を図ってまいります。
基本目標の2つ目は「生涯にわたって自分らしく暮らせるまちづくり」です。
<生涯を通じた健康づくりの充実>
生涯を通じた健康づくりの充実につきましては、生涯にわたり心身ともに健康的に過ごすためには、食育・栄養、運動の観点において、適切な生活習慣を継続することがとても大切です。栄養のバランスの取れた食事をすることや、運動習慣を身に付けることは、生活習慣病のみならず、加齢による筋力の低下や関節等の病気などにより運動機能が衰えて、要介護リスクの高い状態を表す運動器症候群いわゆるロコモティブシンドロームの予防につながり、心身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことが期待されます。
こうした、町民の健康増進を促進するため、町では各関係団体と連携しながら、健康づくりに取り組んでまいります。
また、疾病の重症化予防としての予防接種事業においては、国が65歳を対象とする帯状疱疹定期予防接種について町では50歳以上全員を対象として行ってまいります。
加えて、老朽化が課題であった健康管理センターの代替施設を役場南側、現在は駐車場として利用している土地の西側に、5月頃着工し、令和8年度の利用開始をめざして建設を進めてまいります。
<高齢者の健康づくりの充実>
次に、高齢者の健康づくりの充実につきましては、令和6年12月1日時点における本町の65歳以上の高齢者が13,575人と前年同期と比べ49人増加し、高齢化率も27.7パーセントと前年同期より0.2ポイント上昇していることを踏まえ、介護予防や、地域における支えあいの体制づくり、高齢者社会参加に引き続き取り組む必要があります。
生きがい創出と社会参加の促進、介護予防・認知症予防に向けた取り組みとして行っているeスポーツ事業、高齢者運転免許自主返納等支援事業に加え、本年度からは、加齢に伴い聴力低下となるヒアリングフレイルの周知のため、高齢介護課に関連するイベント等で、アプリを使った簡易的な耳の聴こえのチェックを行ってまいります。
また、高齢者をはじめとした地域住民が活動主体となって、地域にある集会所等を活用して、高齢者の方々が「日常的に」「お住まいの地域で」「地域の方々とふれあう」ことができる場である通いの場等に出向き、フレイル予防の三つの柱である、栄養、運動、社会参加について周知することで、高齢者の方々が主体的に健康づくりや生活習慣の改善に取り組めるような支援を引き続き行ってまいります。
<地域福祉の充実>
次に、地域福祉の充実につきましては、住民の複雑化・複合化した生活課題が顕著となり、地域から孤立化するおそれがある中、あらゆる支援機関と連携のもと相談支援体制の充実・強化に取り組んでまいります。
また、本年度からスタートする「寒川町みんなの地域福祉つながりプラン」の「みんなでつながり 支え合うまち さむかわ」という基本理念のもと、地域福祉の充実の実現に取り組み、地域住民が生きがいを持って、つながり、助け合う地域共生社会をめざしてまいります。
<障がい福祉の充実>
次に、障がい福祉の充実につきましては、「地域の中で安心して暮らせる社会を目指して」という「寒川町障がい者福祉計画」の基本理念のもと、より専門的な支援ができる体制を構築してまいります。
また、本年度から、新たに、災害による停電など不測の事態に備え、在宅で、たん吸引や人工呼吸器を使用している医療的ケア児者等が、安心して在宅生活をおくることができるよう非常用電源装置を日常生活用具の対象品目に追加して、日常生活用具給付事業を拡充してまいります。
<高齢福祉の充実>
次に、高齢福祉の充実につきましては、医療・介護・予防、及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の推進に引き続き努めるとともに、認知症対策につきましては、早期対応ができるよう認知症・健康相談、普及啓発活動等を引き続き行ってまいります。
また、高齢者向けのサービス事業としては、指定収集場所へごみ出しが常時困難な世帯を戸別に訪問して、町が指定する日にごみを収集し、併せて希望する方の安否確認と衛生的な生活環境の改善を図る「ねたきり高齢者世帯等一般廃棄物戸別収集運搬」につきましては、本年4月1日からのごみ、資源物の収集方法の変更に併せ、収集回数を見直しいたします。
基本目標の3つ目は「こころ穏やかに暮らせるまちづくり」です。
<脱炭素・気候変動適応の推進>
脱炭素・気候変動適応の推進につきましては、町、町民、事業所が一体となって2050年までに「二酸化炭素排出実質ゼロ」とすることを目標として、地域の脱炭素化を進めてまいります。
推進にあたっては、町民の脱炭素化への参画が必要不可欠であることから、従来の補助金から寒川版地域通貨である「さむかわPay」の行政ポイント付与により支援する方式に移行したゼロカーボン推進対策設備等導入に係る助成事業を実施してまいります。
また、令和6年3月に締結した東京ガス株式会社との「カーボンニュートラルな未来へのまちづくり連携協定」に基づき、町の未来を担う子どもたちを対象として、省エネをはじめとした環境エネルギー教育の出前授業を行い、「脱炭素化がなぜ必要なのか」も含め、地球温暖化防止等への理解を深めてまいります。
<住環境の向上>
次に、住環境の向上につきましては、耐震改修工事よりも比較的安価に設置が可能な耐震シェルター等を新たに補助対象に加えるほか、建物の耐震化及び危険なブロック塀の撤去等の促進に取り組んでまいります。
また、老朽化した街区表示板を、町のブランドカラー仕様の街区表示板に順次更新してまいります。
<資源循環の推進>
次に資源循環の推進につきましては、ごみの最終処分場を持たない本町にとっては、町民皆様がごみの減量化、資源化を行い、ごみ排出量の減量を進める必要があります。
資源物の収集においては、排出場所や収集回数を改善することで、資源物の適切な分別の推進に加え、より多くの資源物の回収が見込まれることから、本年度より町内に約200カ所ある資源物置場を廃止し、約1,660カ所ある身近なごみ集積所に出せるように変更し、びん・かん・ペットボトルの収集を月1回から月2回に変更してまいります。
また、本年2月にキリンビバレッジ株式会社と締結いたしましたペットボトルの水平リサイクルに関する協定に基づき、町民皆様から回収したペットボトルを、湘南工場で新たなペットボトルに再生利用することで、循環型社会及び地域内循環の実現につなげてまいります。
さらには、家庭から排出される剪定枝については、本年度から月1回の収集日を設け、排出量の状況把握や資源化に向けた調査検討を進めてまいります。
食品ロス対策としては、町民皆様と共通認識を図りながら、フードドライブの開催などを通して、削減に向けて取り組んでまいります。
基本目標の4つ目は「安全・安心に暮らせるまちづくり」です。
<防災対策の充実>
防災対策の充実につきましては、町民一人ひとりが防災や減災に対する意識を持ち、自主防災組織が主体となった災害に強い地域づくりを構築できるよう、各種防災訓練をはじめ、研修会や講演会など、町民が自ら体験し、学ぶ機会を提供しております。また、防災意識の向上と平時からの備えを図るとともに、自主防災組織が災害時に効果的な活動ができるよう、避難生活や救護等に必要な資機材等への確保に対する支援を行い、防災活動を組織的に取り組む体制の強化を図っております。
大規模な災害から生命や財産を守る取り組みにつきましては、地域防災計画をはじめとする災害等に関する計画に基づき、避難所用ワンタッチパーテーションの備蓄を増やすなど避難所の良好な生活環境の整備や災害に強く安全性の高いまちづくりを推進するとともに、被災時において、迅速な復旧復興ができるよう、引き続き防災・減災の強化・充実を図ってまいります。
また、日ごろから、洪水及び内水ハザードマップやマイタイムライン、寒川町防災ハンドブックを活用した啓発活動を通じ、在宅避難を含めた避難行動の周知・啓発を継続するとともに、新たに町民が好きな時間に訓練ができる「デジタル避難訓練」を実施いたします。
さらに、災害時対応を参加・体験できる防災講演会や自主防災組織の訓練及び「さむかわ安全・安心フェア」を継続実施し、幅広い世代の参加を促し、町民の防災意識の向上を図ってまいります。
<消防団体制の充実>
次に、茅ヶ崎市との常備消防の広域化後のさらなる消防力の向上につきまして、茅ヶ崎市消防署宮山出張所の整備を進め、令和8年4月の供用開始に向け、茅ヶ崎市消防本部及び事業者との調整を引き続き行うとともに、消防団体制の充実につきましては、実践的な訓練の導入、新たな教育システムの構築、分団員が防災士の資格を取得するなど、大規模災害時の対応強化のため、町消防団の機動的な体制づくりを引き続き進めてまいります。
<交通安全・防犯対策の充実>
次に、交通安全・防犯対策の充実につきましては、茅ケ崎警察署と連携し、未就学児や小学生、高齢者を対象とした交通安全教室や防犯教室を開催するほか、キャンペーンなどを実施し、広く意識の向上を図ってまいります。
また、防犯パトロールを継続的に実施するとともに、防犯灯の増設を含め適正管理を行い、安全・安心のまちづくりの実現を図ってまいります。
基本目標の5つ目は「時代に最適化したにぎわいのあるまちづくり」です。
<道路の整備>
道路の整備につきましては、県道45号丸子中山茅ヶ崎と町道大蔵宮山8号線が交差する小谷交差点は、小谷小学校の通学路に指定しておりますが、交通量や大型車両の右左折も多く、大型車両による巻き込み事故等が懸念されておりました。
特に、交差点の西側は、車道幅員が広く歩車分離されていないことから、歩行者の安全確保に向け、本年度は、小谷交差点より西側に向け歩道の整備工事を実施いたします。
また、県道45号丸子中山茅ヶ崎とJR相模線の香川駅を結ぶ町道大曲14号線は、南小学校の通学路上にあり、現況幅員は狭く、朝晩を中心に交通量が多く交通事故が懸念されていることから、道路の幅員を拡幅し、歩行者の安全確保に向け、本年度は事業区間残り3分の1について、歩道整備工事を実施いたします。
<公共交通網の整備>
次に、公共交通網の整備につきましては、将来に向け、町民の移動手段の確保に資するための「寒川町地域公共交通計画」に基づき、利便性の高い公共交通の確保・維持など地域における持続可能な公共交通の構築に取り組むとともに、海老名・寒川間の路線バス運行の支援、鉄道事業者との協議に引き続き取り組んでまいります。また、コミュニティバスにおいては、継続運行に取り組むとともに、町民、バス事業者、関係行政機関などを構成員としたこれまでの地域公共交通会議に加え新たに設ける運賃等協議会において、より高齢者が利用しやすいよう運賃の見直しを図ってまいります。
<下水道の整備>
次に、下水道の整備につきましては、近年の集中豪雨や都市化等による浸水被害により、水害に対する町民皆様の意識が高まっており、浸水被害の解消が求められております。
雨水につきましては、排水能力や貯留機能の向上のため、雨水管理総合計画に基づき雨水幹線枝線整備を行うとともに、小出川河川改修に伴う岡田八丁目地内の雨水吐け口を整備し、効果的な浸水対策を図ってまいります。
また、雨水幹線の浚渫等の維持管理事業や、水位計等による内水浸水の監視などソフト事業と併せて、引き続き浸水対策を行ってまいります。
なお、下水道施設の持続的かつ効果的な維持管理を推進するため、ウォーターPPPの導入に向けた可能性調査を実施してまいります。
<市街地整備の推進>
次に、市街地整備の推進につきましては、 町の新たな産業集積拠点として整備を進めている組合施行の田端西地区土地区画整理事業において、地区内の公共施設である道路、下水道、公園が整備されたことから、本年度は換地計画の認可業務に助成することで、事業期間内に土地区画整理事業が完了するよう組合に支援を行ってまいります。
ツインシティ倉見地区整備事業におきましては、新駅周辺整備検討区域を中心とした土地利用や骨格施設等について、神奈川県と共同で行う調査等を通じて具現化に向けた検討を一層進めるとともに、町が主体となり関係権利者向けの説明会や勉強会等の開催を通じて、まちづくりに対する合意形成を図ってまいります。
併せて、事業費の負担割合やJR東海への技術相談につきましても、引き続き県と調整を進めてまいります。
<商業の振興>
次に、商業の振興につきましては、地域の活性化を目的に、地域経済の循環をめざし、その手段として商工会が中心となって、デジタル地域通貨「さむかわPay」を導入し、町も支援しております。さむかわPayは加盟店で使用することができるキャッシュレス決済アプリです。今後は、町の施策とも連携し、ポイントの付与等も実施してまいりますので、さむかわPayを活用していただくことにより、地域がつながる、にぎわいのあるまちづくりをめざしてまいります。
<工業の振興>
次に、工業の振興につきましては、意欲ある地域企業が活動しやすいビジネス環境を整え、関係機関及び関係団体と連携を図りながら、企業の成長ステージに応じた支援体制を構築してまいります。
また、企業等の立地促進に関する条例に基づき、製造業をはじめ、情報通信業や研究施設のほか、町の経済に新たな活力をもたらす企業を誘致するための施策を検討してまいります。
<農業の振興>
次に、農業の振興につきましては、農業者の高齢化と担い手の不足など、既に顕在化する課題に対応するための方策を計画的に振興するため、(仮称)農業ビジョンの策定を進めてまいります。
また、農業基盤の整備については、老朽化した農業用排水路の整備維持補修を進めてまいります。
さらに、近年増加傾向にある遊休農地の活用に向け、農業委員、農地利用最適化推進委員等と協力しながらマッチングを進め、農地の適正な維持管理を図るとともに、新規就農者や新たな法人等の参入など、積極的に地域農業の担い手確保に引き続き取り組み、農福連携等に対する取り組みへの推進や農地の集約化等を図ってまいります。
基本目標の6つ目は「まちづくりのための基盤づくり」です。
<町民との協働によるまちづくりの推進>
町民との協働によるまちづくりの推進につきましては、本町のまちづくりの最高規範である自治基本条例の本旨にのっとり、町民皆様と町が、自治の担い手としてそれぞれの責任を果たしながら、相互に補完し、協力し合ってまちづくりを進めているところでございます。
自治基本条例に基づき設置されている、まちづくり推進会議では、町民参加による自治運営の推進を図るため、町政運営に対する町民皆様の参画等に関することを協議し、町に報告・提案していただいております。
また、自治会加入率の低下及び役員の担い手不足が課題となっていることから、自治会加入促進について、自治会長連絡協議会と連携し、魅力ある自治会活動の情報発信の支援及び未加入者に対する自治会加入を促進してまいります。
ボランティア団体等登録制度に登録されているボランティア団体につきましては、その活動等に関する周知を図るとともに、ボランティア団体の現状を把握してまいります。
<自律的な行財政運営>
次に、自律的な行財政運営につきましては、少子高齢化・人口減少など将来を見据えた上で、社会情勢や人々の価値観の変化をしっかりと捉えながら様々な取り組みを進め、町民皆様に「寒川に住んでよかった」、「住み続けたい」と思っていただけることが重要であると考えております。
これまで、「町の魅力と認知度の向上」を目的に、『「高座」のこころ。』をスローガンとしたブランド展開として、移住定住ポータルサイトやSNSなど様々な媒体を通じて、町の魅力発信やロケ地誘致の推進、ブランドマークの可視化などによる町の認知度向上とブランドの浸透を図ってまいりました。
その結果、一定程度寒川町は認知されてきておりますが、移住を検討している方が寒川町で暮らす、より具体的なイメージが掴めるように本年度は、新たな取り組みといたしまして、移住検討者に対し、最も効果的な情報提供先となる移住定住ポータルサイトのさらなる充実を図るため、先輩移住者の声などを掲載するコンテンツを新設し、移住検討者に対して寒川町での暮らしをイメージしやすい情報の提供に努めてまいります。
さらに、移住定住ポータルサイトへ効果的に誘導するための仕掛けを構築することにより移住候補地から移住地へ昇華に取り組んでまいります。
また、寒川町を町内外へ効果的にPRしていくためには、行政による情報発信に加え、町民や寒川町を応援していただける方による口コミが必要不可欠です。寒川町への愛着心を醸成し、町を好きになってもらうことにより、町民等による情報発信の担い手を創出し、ブランドコミュニケーションの確立に努めてまいります。
ふるさと納税推進事業につきましては、財源確保を目的として、令和6年度は新たに複数のふるさと納税サイトを開設しました。本年度は新たに設置される資産経営課へ事務移管することで庁内体制の充実を図り、より効率的・効果的な事業実施が可能となることで、さらなるサイトの拡充や、新たな地域資源の掘り起こしなどによる返礼品の充実に努めるとともに、特産品をはじめとした自治体の情報発信手段としても活用し、引き続き財源確保に向けた取り組みを推進してまいります。
<まちづくりを支える組織と基盤づくり>
次に、まちづくりを支える組織と基盤づくりにつきましては、人口減少社会に加え、変化が激しく予測が難しい時代を迎えている中では、様々な社会環境の変化や多様化・複雑化している町民ニーズに対し、的確かつ柔軟に対応できる「職員の育成」と「人材の確保」、さらには「組織力の強化」が、各施策推進にあたって大変重要なテーマであると認識をしております。
そうしたことから、各施策の推進を支えることとなる職員の「質・能力の向上」と「組織力の強化」を図るため、町職員としての愛着心の醸成はもとより、各階層における課題に向き合った研修等の展開を引き続き進めてまいります。
本年度における新たな取り組みとしては、特に若手職員の仕事に対する価値観の変化を踏まえつつ、大きな課題となっている「若手職員の離職抑制」や「モチベーションの向上」、さらには、職員一人ひとりのスキルアップとデジタルトランスフォーメーションの推進による「組織の生産性向上」を目的とした「職員の資格取得に対する助成制度」をスタートするなど、今後も人事を取り巻く様々な課題解決に向け、積極的に人材育成に取り組んでまいります。
加えて、RPAや生成AIなどのデジタル技術とデータの活用を推進し、業務効率化により新たな業務時間を創出することで、人的資源をサービス向上につなげ、町民の利便性の向上を図ってまいります。
いずれにいたしましても、「公務員のなり手不足」や「業務の複雑化・増大化」など、公務を取り巻く環境が、ますます厳しさを増す中ではありますが、町民皆様に対し、質の高いサービス・満足度の高いサービスを持続的に提供すべく、職員の「育成と確保」を積極的に進めるとともに、職員一人ひとりの生産性向上と組織力の強化を図ってまいります。
少子高齢化・生産年齢人口の減少が見込まれる中、限られた予算・人材を有効に活用し、複雑・多様化する町民ニーズに対応した質の高い町民サービスを提供することが求められていることから、RPAや生成AIなどのデジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション推進を図ることで、業務効率化と住民の利便性の向上を図ってまいります。
(令和7年度予算)
令和7年度予算につきましては、町のブランドスローガン『「高座」のこころ。』に表わされる「穏やかさ、優しさ、あたたかさ」を念頭に置き、「寒川町総合計画2040」に掲げるまちの将来像である「つながる力で 新化するまち」の実現に向け、「寒川町総合計画2040第2次実施計画の効率的、効果的な推進」、「社会経済情勢等の変化に対応した取り組みの推進」、「持続可能な行財政運営の取り組み」の3つの予算編成基本方針のもと、編成いたしました。
歳入の一般財源の根幹をなす町税については、賃上げなどの影響により課税所得が上昇する見込みであります。また、昨年度の定額減税の影響が解消されることなどの理由により、滞納繰越分を含めた町税の総額を91億9,370万円と見込み、対前年度比では4.7%の増といたしました。
予算規模といたしましては、一般会計総額は196億4,000万円、対前年度比11.5%の増とし、過去最大となっております。その上で、国民健康保険事業特別会計をはじめとする4特別会計を合わせた全会計の予算総額は、317億8,842万円、対前年度比で6.5%の増といたしました。
(おわりに)
以上、令和7年度の町政運営にあたっての基本的な考え方と主な事業ならびに令和7年度予算の全体像につきまして、ご説明させていただきました。
地震や風水害をはじめとする激甚化・頻発する自然災害やコロナ禍を経てライフスタイルや働き方などが急激に変化し、町民皆様のニーズも複雑・多様化する中で、行政には迅速な対応が求められております。
このような状況の中、町民皆様と町が、安全・安心、環境、健康をはじめとする様々な取り組みを、ともに進めていくことで、一歩先の安心を感じていただき、こころ豊かな暮らしにつながるよう、全力を傾注してまいります。
町民皆様が笑顔で暮らし、「寒川に住んでよかった、住み続けたい」と思われるまちづくりの実現をめざしてまいります。
つきましては、議員各位をはじめ、町民皆様のより一層のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、私の令和7年度の施政方針といたします。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課企画マーケティング担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:231、232)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ

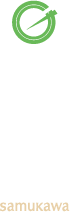


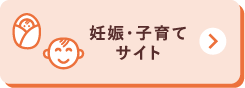
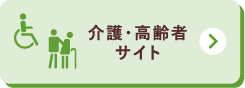





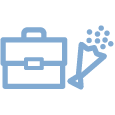





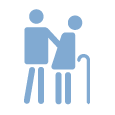

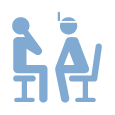



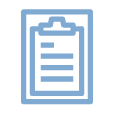

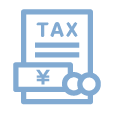

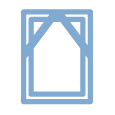

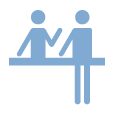



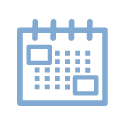





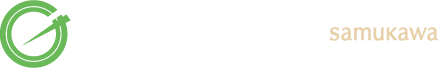
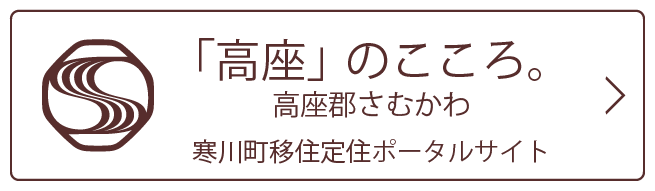
更新日:2025年03月05日